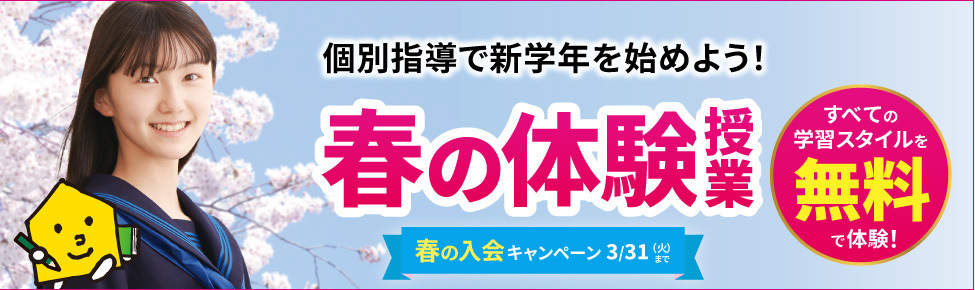学力検査では、中学校で習ったことをどれだけ理解しているかが試されます。最近は、知識だけでなく「思考力・判断力・表現力」が重視され、「資料の読み取り」や「自分の考えや結果に至った理由を述べる」といった、覚えた知識を活用する問題が多くなっています。こうした入試問題の出題傾向を知っておくことで、受験勉強で必要な対策がわかります。
英語
2026年度/令和8年度
出題傾向
第一問はリスニング。第二問は文法・語法問題と昨年追加された資料読解問題も出題されました。第三問、第四問は長文読解、第五問は英作文で構成されています。平均点は55.5点であり、昨年度の50.4点と比べて、例年並みの平均点に戻りました。 早い段階で基本的な単語や文法の知識を習得し、配点が高く差がつきやすい長文読解や英作文の対策に十分な時間を割くことが重要です。教科書内容の学習とあわせて、実戦的な問題演習を重ねることで、入試で問われる「読む」「聞く」「書く」の三技能をまんべんなく鍛えておく必要があります。
対策のポイント
長文読解の練習を!
毎年のように長文の単語数が増えており、一つひとつの単語も難しくなっています。また、出題の仕方もチラシやメール、近年宮城県公立入試では英語スピーチの読解問題が通例となっており多種多様です。入試までに様々な英文に触れ、慣れておくことが必要です。
リスニングも日頃から練習を積んでおこう
第一問は、例年、リスニング問題。令和7年度は記号選択問題が7題、対話に沿う英文を記述する英問英答問題が1題出題。一通りの文法を学習し終えたら、公立高校入試などのリスニング問題を用いて様々なパターンの練習をするとよいです。英文原稿を活用しながら何度も英文を聞き、音声を真似して抑揚をつけての音読も効果的です。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスニング | 正しい答えを選ぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 絵や地図を使う | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メモ・グラフ・表を完成する | − | − | − | − | |
| 日本語[英語]で答える | − | − | − | − | |
| 自分の考えを英語で書く | − | − | − | − | |
| 発音・アクセント | 発音・アクセント | − | − | − | − |
| くぎり・強勢・抑揚 | − | − | − | − | |
| 読解 | 英文和訳(記述) | − | − | − | − |
| 脱文挿入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | − | − | − | − | |
| 要旨把握 | − | − | − | − | |
| 語句解釈 | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指示語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 会話文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文法・英作文 | 和文英訳 | − | − | − | − |
| 単語の穴埋め | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 正誤問題 | − | − | − | − | |
| 言い換え・書き換え | − | − | − | − | |
| 英問英答 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 条件英作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自由英作文 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| リスニング | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 英作文 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数学
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数は4題で小問数は25問の構成であり、ここ数年間ほぼ同様の形式です。問題構成や出題形式に大きな変化はありませんが、教科書に掲載されている例題や問い、基本の問題が48点分、応用問題の出題が41点分、教科書に類題がないような形式の発展問題の出題が11点分と、応用問題の出題増加し難化傾向にありました。特に、題意を正しく理解し、その上で正しく計算して答えを導く「読解力、思考力、判断力」を問うような難問も増加傾向にあります。
対策のポイント
基礎知識・基礎計算が何よりも重要!
応用問題が増えているからこそ、基礎問題を落としてしまうのは致命的です。例年、約50点分は基礎問題であるため、それらを取り切り応用問題でいかに点数を上乗せできるかが勝負です。模擬試験などで、大問1や各問の(1)でミスがある場合は、基本問題の復習から徹底しましょう。
大問三・四で差をつけよう!
宮城県の入試では大問三で1次関数、大問4で図形(証明など)が出題されるのが定番。近年では思考力を問うような応用問題も増えてきていますが、1次関数や証明は細かな設定は変わっても、考え方・書き方はお決まりのものばかり。練習次第で必ず解けるようになるので、これらをしっかり得点しライバルと差をつけよう!
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数と式 | 正負の数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 文字式 | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 方程式・不等式 | − | ◯ | − | − | |
| 式の計算 | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 連立方程式 | − | ◯ | − | − | |
| 平方根 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 多項式 | − | − | − | − | |
| 2次方程式 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 関数 | 比例と反比例 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 1次関数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 y = ax2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 図形 | 平面図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 空間図形 | − | − | − | ◯ | |
| 平面図形と平行線の性質 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 図形の合同 | − | − | ◯ | − | |
| 図形の相似 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 円周角と中心角 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 三平方の定理 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| データの活用 | データの分布・比較 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 確率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 標本調査 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小問数 | 25 | 25 | 26 | 25 | |
| 記述問題 | 図形の証明(説明) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の説明・証明など | − | − | − | − | |
| 立式・解法の過程の記述 | − | − | − | − | |
| 作図(図形) | − | − | − | − | |
| 作図(グラフ) | 1 | − | 1 | 1 | |
国語
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問構成は全6題で前年からの変更はなく、全体の設問数や配点もほぼ変化はありませんでした。 平均点が前年の59.0点に対して58.6点であったことから、難易度も前年と大きな差異は無かったと言えます。古典分野においては前年に続き古文が出題されましたが、令和4年度及び5年度では2年連続で漢文が出題されているため、今後の入試に向けては古文と漢文のどちらが出題されても対応できるようにしっかりと学習を進めておく必要がある点は留意しておきたい。
対策のポイント
文学的文章は心情変化と情景描写に注意!
第三問は文学的文章の問題でした。記述問題と書き抜き問題の出題が多いですが、高得点を獲得するためには、文章の主題を意識して要点をまとめなければなりません。普段の練習から登場人物の心情変化や情景描写を見逃さずに読み取る訓練を積みましょう。また記述問題を遠ざけないで日頃から手を動かすことも大切です。
作文の練習は必須!
第六問の作文問題では「言葉の変化」についての考えを160~200字で記述する問題でした。作文の配点は20点と高いため、過去問題などで論理的に自分の意見を書く練習と時間を短縮させるためのコツを身につけて置く必要があります。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢字・語句 | 漢字(読み・書き・筆順・画数・部首) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 熟語(三字熟語・四字熟語) | − | − | − | − | |
| 語句(ことわざ・慣用句) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文法 | 文と文節 | − | − | − | − |
| 品詞・用法 | − | − | − | − | |
| 敬語、その他 | − | − | ◯ | − | |
| 表現・情報 | グラフ・図表の読み取り | − | ◯ | − | − |
| 話し合い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 伝え方の工夫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 課題作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聞き取り問題 | − | − | − | − | |
| 文学史 | 文学史 | − | − | − | − |
| 現代文(読解) | 主題・表題 | − | − | − | − |
| 大意・要旨 | − | − | − | − | |
| 情景・心情 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文脈把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文章構成 | − | − | − | − | |
| 指示語 | − | ◯ | − | − | |
| 接続語 | − | − | − | − | |
| 脱文・脱語補充 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 古典 | 古文のかなづかい・古語 | − | − | ◯ | ◯ |
| 古文の会話・主語 | − | − | − | − | |
| 古文の展開 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 文章のジャンル | 論説文・説明文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 記録文・報告文 | − | − | − | − | |
| 小説・伝記 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 随筆・紀行・日記 | − | − | − | − | |
| 詩 | − | − | − | − | |
| 和歌(短歌) | − | − | − | − | |
| 俳句・川柳 | − | − | − | − | |
| 古文 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | ◯ | ◯ | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 小問数 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 記号解答 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 記述式解答(漢字の読み書きも含む) | 20 | 18 | 20 | 20 |
理科
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数・小問数ともに例年からの大きな変化は見られませんでした。各大問の内容は、第一問が4分野からの小問集合、第二問が化学分野、第三問が地学分野、第四問が物理分野、第五問が生物分野でした。それぞれの大問の出題形式は、実験およびその実験結果に対して考えさせるもので例年と同様。平各分野からバランスよく出題されていて、学校ではあまり時間をかけて扱わない「自然環境」に関する分野の問題も出題。教科書に記載されている基本的な内容を中心とした出題が今後も予想されます。
対策のポイント
実験・観察・作図なども要注意!
実験や観察に関しては細部まで踏み込んだ問題も出題されることがあるので、教科書に記載されている実験、観察はよく確認しておきましょう。また、記述・計算・作図問題は合わせて10問程度出題されるので、各単元でよく出題される問題は演習を行い、慣れておくことが大切です。
学年・分野偏りなく勉強を!
宮城の傾向として学年や分野に偏りがなく広範囲で出題されるため、早い時期から受験勉強を始めて全範囲を何回も繰り返して解きなおすことが大切。中3夏までは基礎知識を徹底復習。夏以降は計算・記述・作図などの応用問題演習と、計画的に受験勉強をしましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 力のはたらき | ◯ | − | − | − |
| 光と音 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 電流 | − | − | ◯ | − | |
| 電流と磁界 | − | ◯ | − | − | |
| 力のつり合いと合成、分解 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 運動の規則性 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 仕事とエネルギー | − | ◯ | − | − | |
| 化学 | 物質のすがた | − | − | ◯ | − |
| 水溶液 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 状態変化 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 物質の成り立ち、原子・分子 | − | ◯ | − | ||
| 物質の化学変化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 化学変化と物質の質量 | − | ◯ | − | − | |
| 水溶液とイオン、電池とイオン | ◯ | − | − | ◯ | |
| 化学変化と電池 | ◯ | − | − | − | |
| 生物 | 生物の観察と分類の仕方 | − | − | ◯ | |
| 生物の体の共通点と相違点 | − | − | − | − | |
| 生物と細胞 | − | ◯ | − | − | |
| 植物の体のつくりと働き | − | − | − | ◯ | |
| 動物の体のつくりと働き | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 生物の成長とふえ方 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 遺伝の規則性と遺伝子 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 生物の種類の多様性と進化 | − | − | − | − | |
| 地学 | 身近な地形や地層、岩石の観察 | ◯ | ◯ | − | − |
| 地層の重なりと過去の様子 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 火山と地震 | ◯ | − | − | ◯ | |
| 自然の恵みと火山災害・地震災害 | ◯ | − | − | − | |
| 気象観測 | − | − | ◯ | − | |
| 天気の変化 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 日本の気象 | − | ◯ | − | − | |
| 自然の恵みと気象災害 | − | − | − | − | |
| 天体の動きと地球の自転・公転 | ◯ | − | ◯ | − | |
| 太陽系と恒星 | − | − | ◯ | ||
| 分野融合 | エネルギーと物質(物理・化学) | − | − | − | − |
| 自然環境の保全と科学技術の利用(化学・生物) | − | − | − | ◯ | |
| 生物と環境(生物・地学) | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 35 | 35 | 32 | 32 |
| 記号解答 | 18 | 21 | 19 | 21 |
| 短文記述 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 計算問題 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 図・グラフ、モデル | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 語句記述 |
社会
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問6問、小問30問の出題数は昨年同様でした。各大問の主な内容は、第一問が歴史と公民の融合問題、第二問が日本地理総合問題、第三問が歴史総合問題、第四問が公民総合問題、第五問が世界地理総合問題、第六問が歴史と公民の融合問題でした。 出題形式は、語句記述問題が6問で合計18点分であり、例年よりも1問増加しました。記号選択問題が19問で合計57点分であり、例年よりも1問減少し資料読解型の文章記述問題が5問で合計25点分であり、例年通りでした。 平均点は、昨年度59.6点に対し今年度は56.1点でした。
対策のポイント
資料読解型の文章記述問題ができるかが合否の分かれ目!
宮城県公立高校入試問題では5問25点分の資料読解記述問題でいかに高得点を獲得できるかが合格のカギ。基本的な知識事項をしっかり習得し、資料読解の演習を重ねて思考力を養い、正確に記述する表現力を鍛えることが必要です。
資料を読解する着眼点を養おう!
宮城県公立入試では教科書や資料集には掲載されていない初見の資料が出題され、複数の資料を関連付けて思考する力が求められます。そのため、過去問の演習や資料を読解する際の着眼点の見つけ方、複数の資料を論理的に結びつける思考力を養う必要があります。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理的分野 | 日本の姿 世界の姿 |
地形 | − | ◯ | − | − |
| 気候 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 人口 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| 産業・貿易 | 第一次産業(農林水産業) | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 第二次産業(工業) | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 第三次産業(商業・サービス業) | − | − | − | − | ||
| 貿易 | − | − | − | − | ||
| 地域 | アジア州 | − | ◯ | ◯ | − | |
| ヨーロッパ州 | − | ◯ | − | − | ||
| アフリカ州 | − | − | − | ◯ | ||
| 南北アメリカ州 | ◯ | − | − | − | ||
| オセアニア州 | − | − | − | − | ||
| 九州地方、中国・四国地方 | ◯ | − | − | ◯ | ||
| 近畿地方、中部地方 | − | ◯ | − | − | ||
| 関東地方、東北地方、北海道地方 | − | − | ◯ | − | ||
| 歴史的分野 | 日本史 | 平安時代まで | ◯ | − | ◯ | ◯ |
| 鎌倉・室町時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 戦国・江戸時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 明治時代以降 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 世界史 | 古代 | − | − | − | − | |
| 中世 | − | − | − | − | ||
| 近世 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 近・現代 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| テーマ史 | 政治・外交史 | − | − | − | − | |
| 社会・経済史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 文化史 | ◯ | ◯ | − | − | ||
| 公民的分野 | 政治 | 現代社会と私たちの生活 | − | ◯ | − | − |
| 個人の尊重と日本国憲法 | ◯ | ◯ | − | ◯ | ||
| 現代の民主政治、三権分立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 地方自治 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 経済 | 消費生活と流通 | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 企業と生産活動 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ||
| 財政、国民生活と福祉 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 国際 | 地球社会と私たち | ◯ | − | − | ◯ | |
| 経済と貿易 | ◯ | − | − | − | ||
| 環境問題 | − | − | − | − | ||
| 時事問題 | − | − | − | − | ||
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 小問数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 記号解答 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 用語記述 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 文章記述 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 作業・作図 | − | − | − | − |