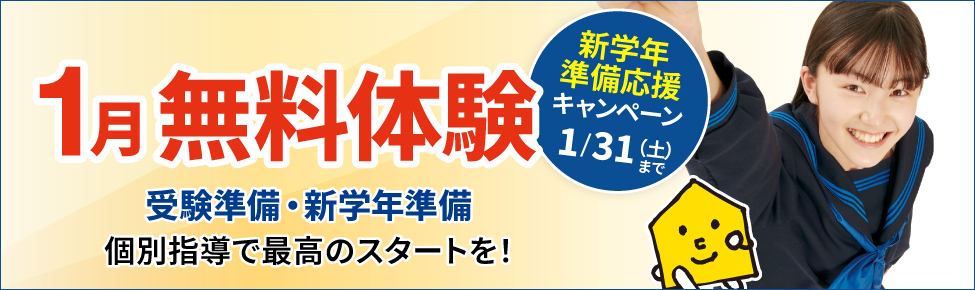中学で国語が嫌いになる生徒に見られる「2つの予兆」
小学生の時にはそんなに苦手でもなかったのに、中学に入ってからなぜか国語の点数が伸びなくなった…。そんな生徒に見られる二つの予兆があります。それは、
① 文章の内容に興味が持てない
② 記述問題が書けない
これは、中学校の国語が小学校の国語に比べ、急激に難易度が上がることによって起こります。
予兆1「文章の内容に興味が持てない」
興味が持てない理由は、「知識」が足りないから
中学国語の現代文には、評論文、随筆、小説など、小学校では扱わなかったジャンルの文章が登場し、その内容もより「大人の知識」を必要とするものが増えてきます。
「書かれている文章に興味を持てない」のは、そこに書かれてあることに共感したり納得したり、あるいは反対する気持ちなどが起こらないからです。
文章を読んで、その文章に何かしらの感情を抱くには、書かれていることに関するイメージを持たねばなりません。
それがなく、よくわからないことをツラツラと読むだけでは、興味など持てるはずがありません。
つまり、「興味がわかない」のは、その文章に関するこれまでの経験や知識が不足しているのです。
「読み解く力」に知識がどれぐらい影響しているのかを示す事例があります。
2010年のセンター試験の国語では、小説の問題に吹奏楽をテーマとした「楽隊のうさぎ」(中沢けい)が出題されました。この問題の正答率に関して、ある傾向がはっきりと表れたのです。
部活動などで、吹奏楽の経験を持っている生徒の方がより正答率が高かったのです。
吹奏楽を経験したことがない生徒には、文章に書かれてある楽器名すらピンとこない。その扱い方や指の動きなどおよそイメージがつかず、いちいち突っかかります。
一方、吹奏楽を経験したことがある生徒なら、文章の大半をすんなりと読むことができ、自分の中にしっかり映像も浮かび上がります。
ですから、たとえば心情理解を問う問題などでも、「明らかに間違っている回答」を見つけるのにはさほど時間がかからないのです。
知識量を増やすには?
では、どうすれば知識を増やせるのでしょう? これはもう、いろんなことを経験したり、あるいは本や新聞を読んだりといった「日常的な学び」を継続するしかありません。
ただし、やみくもに「本を読め、頑張れ!」と言っても、これもまた無理。まずは、興味をあることや好きなことに関する本などから始めてください。
たとえどんなに好きなことであっても、必ず「未知」には出会います。好きなことならその未知を調べることにも喜びを感じます。調べればまたさらなる未知に出会います。
こうして出会った「未知」を「既知」に変え、蓄積していくことで知識量を増やしていくのです。
一つずつしっかりと。遠回りのように思えても、結果的にはそれが一番の近道です。
予兆2「記述問題が書けない」
記述問題が書けないのは、文章の「型」を知らないから
もう一つ、小学校から中学校になって大きく変わるポイントがあります。
それは、記述問題が増えることです。よく出る記述問題は、概ね次の4つに分類されます。
【よく出る記述問題4パターン】
| 番号 | 記述問題の パターン |
例 |
|---|---|---|
| ① | 傍線部を言い換える記述問題 | 傍線部の「AIによる社会の目まぐるしい変化」とは、どんな変化を指しているか? |
| ② | 理由や根拠を示す記述問題 | 筆者は、社会が目まぐるしく変化する理由は何だと考えているか? |
| ③ | 登場人物や筆者の 心情を推測する記述問題 |
「テスト結果は85点だった。〇〇さんは唇をかみしめた。」この時の心情は? |
| ④ | 書かれている文章の 要旨をまとめる記述問題 |
この文章を通じて、筆者が読者に最も伝えたいことを100文字以内でまとめなさい |
記述の「型=答え方・書き方のルール」を知る
中学の場合、いずれの記述問題も80~100字程度、つまり1文か2文まででまとめる問題がほとんどです。ということは、「型」を覚えておけば、的外れな文章を書くことはないのです。
ここでいう「型」とは、「答え方・書き方のルール」です。たとえば、傍線部の言い換え問題なら、文中のどこかに必ず「別の言い方で表現している文章」があるはずです。
それを適切に見つけ出して書く。あるいは、理由や根拠が問われているなら、回答文の最後は必ず「‥‥だから」という語句で終わるはすです。
つまり、「問われていることは何かを見極めて、ルールに従って書く」ことが大切です。
また、心情推測問題などでは、文中に示された事実などから論理的に類推する力も求められます。たとえば、上記の「テスト結果は85点だった。〇〇さんは唇をかみしめた。」の一文。
一般的には、85点なら上出来です。ではなぜ「唇を噛みしめた」のか?
平均点が95点で自分だけ劣って「恥ずかしかった」のか?100点を取るとお母さんと約束して猛勉強したにも関わらず失敗して「自分が情けなかった」のか。あるいは、にやけそうになるほどの「喜びを隠す」ために唇をかみしめたのかもしれません。
どれが正解なのか?類推するための材料は必ず文中にあり、それをもとに正しく推測し、記述していくのです。