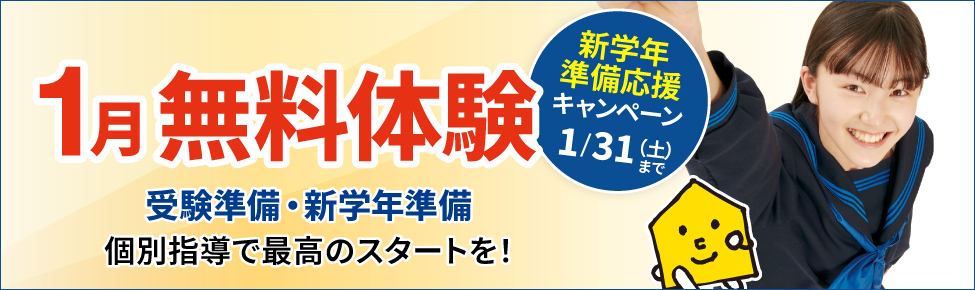高校受験の「社会」を取り巻く環境と出題傾向
![]()
中学校の社会の授業の進み方を理解しよう!
ひと口に「社会」と言っても、その中には3つの学習分野、地理・歴史・公民があります。中学ではこの3分野を3年間かけて学習します。
【各学年での学習単元】
|
1年生 |
2年生 |
3年生 |
地理
| 世界 アジア・オセアニア・ヨーロッパ・
北アメリカ・南アメリカ・アフリカ |
日本 地形と気候・人口と産業・九州/沖縄・中国/四国・近畿・中部・関東・東北・北海道 |
|
歴史
| 文明の起こり~江戸初期 弥生・古墳・飛鳥/奈良・平安・鎌倉・室町・ルネサンスと大航海時代・安土桃山・江戸初期 |
江戸中期~明治 江戸の政治改革・ヨーロッパの近代革命・江戸幕府滅亡・明治維新・日清/日露戦争・近代産業 |
大正~現代 第一次世界大戦・大正デモクラシー・第二次世界大戦・戦後日本と冷戦・冷戦終結と現代 |
公民
| |
|
日本国憲法・基本的人権・国民主権/国会・行政/内閣・司法/裁判所・地方自治・消費・企業/生産・経済/金融・財政/景気・福祉・国際社会 等
|
多くの中学校では、中学1年から中学2年にかけて地理と歴史を交互に進めていきます。地理は2年で終了、歴史も大半は2年で終了し、公民は3年になって履修し始めます。
公立入試での出題比率「地理3:歴史4:公民3」のとらえ方とは?
一般的な公立高校の入試問題の場合、出題分野の比率はおよそ「地理3:歴史4:公民3」となっています。この割合は以前から大きく変化していませんが、3つの分野の枠組みを超えた「分野融合型」の問題が増えているため、各分野のつながりを意識した学習がより重要(暗記だけでは対応できない状況)になってきています。
「知識を問う問題」と「思考力・表現力を問う問題」のバランスとは?
もとより、社会の出題傾向は都道府県によって異なります。比較的単純な「知識問題」が大半を占める都道府県もありますが、必ずその中に、与えられた図表などの資料から①「読み取れることを選択する」問題、②「読み取れる内容の正誤を判断する」問題、③「読み取れたことを自分の言葉で表現する」問題が含まれています。
こうした問題の「出題比率の違い」がその都道府県の出題傾向と言っても良いでしょう。近年はここからさらに④「読み取った内容をもとに自分の意見や考えを述べる」問題も出題する都道府県も出てきています。そのため、詰め込み系の知識だけで時間内に適切な解答をまとめることが難しいことは言うまでもありません。
中には「他の受験生も解けないからこの問題は解かなくてもいい」といった判断をする人もいるでしょうが、本当にそうでしょうか?きちんと対策してきた受験生との力の差は、選択問題のような「偶然の正解」で埋めることはできません。まずは自分が受験する都道府県の社会の出題傾向を把握し、効果的な受験対策を講じるようにしましょう。
[関連ページ]47都道府県別 公立高校入試情報
出題構成は知識(暗記)7割+技能(思考・分析・表現)3割!
これらのことを前提に、公立高校受験における社会の傾向を総括します。出題比率を分野別に捉えると、「地理3:歴史4:公民3」となり、以前からの変化はないように見えますが、「学力の問われ方」として捉えなおすと、近年の出題傾向はおおよそ「知識(暗記)7割:技能(思考・分析・表現)3割」です。
こういった「問題の出題タイプ」別に得点ラインを想定してみると、目標得点としては、一定以上の難易度の高校に合格するなら「全体の7割を占める知識(暗記)問題で9割正答(70×0.9=63点)」+「3割を占める技能(思考・分析・表現)問題で6割正答(30×0.6=18点)」=81点となります。まずは過去問でこの点数をとることを目安に仕上げていきましょう。
(地理1)「自然・環境」から「文化や産業との関連性」を理解しよう!
![]()
世界地理では、「地域ごとの人々の生活」に着目してみてください。それぞれの地域の「自然(地形・気候)」がもたらした「生活環境」から、そこに住む人々がどんな服を着て、何を食料とし、どんな場所(住居)で暮らしていたのかを関連づけて知識を広げていくと分かりやすくなります。
【地理:関連づけて知識を広げる学習】
![【地理:関連づけて知識を広げる学習】]()
この後の人類の歴史では、安定した生活が送れるようになった国や地域から順に「自然から与えられたもので生きていく生活スタイル」を「自然に働きかけて、より豊かな世界を創り出す生活スタイル」に変化させていきます(産業の発達)。
このあたりが理解できてくると、なぜイギリスやフランスなどの国が世界各地に植民地を持つようになったのか、なぜイギリスやフランスより先に世界の海に進出したスペイン・ポルトガルがそうならなかったのか、(地理と歴史の関連性)が見えてきます。
こうした「世界の大きな流れ」や「地域の全体的な特徴」は一旦仕組みを理解できてしまえば、後は「同じとらえ方」で学習を進めることができる(自分で考えられる)ようになります。まずはこうした基本的なものごとのとらえ方(枠組み)を意識してもらいたいです。※特におすすめの国や地域(学習テーマ)は次の項目でご紹介します。
(地理2)「基本となる考え方」をきちんとマスターしよう!
世界地理で特に押さえておきたいのは「ヨーロッパ・北アメリカ」です。これらの地域の共通点は、「①もともとの自然環境とその後の産業の発達との関連性がかなりはっきりしている地域であること(理解しやすい)」「②植民地を支配する側(世界に影響を与える側)として発展してきた歴史を持っている地域であること(流れがつかみやすい)」です。
これらの地域を学習した後は、①の観点から「ヨーロッパ・北アメリカ」の学習内容を「基本の考え方」に置いて、その他の地域を積極的に復習していくことをおすすめします。
また、②の観点をもとに「植民地支配を行った国々(イギリス・フランス・オランダ・アメリカ・スペイン・ポルトガル)」から「植民地支配を受けた(アフリカ・南アメリカ・東南アジア・南アジア)の国々」を見るようにすると、それぞれの国の公用語・宗教人口・産業といった特徴が見えてきます。
このように、どの地域を学習する場合も、偏りなく語句を丸暗記するより理解の軸となる地域を優先的におさえる勉強方法の方が効率的に全体の流れをつかみやすくなることを知っておいてください。
(歴史2)織田信長以降は「日本と世界の2階建て学習」に!
学習のしかたに変化が起こるのは「近世(織田信長・豊臣秀吉の出現)」以降です。ここからは歴史の流れが「①日本を中心としたアジアの歴史」と「②ヨーロッパを中心とした世界の歴史」に分かれ、2階建てになります。
ここで気をつけたいのが「日本と外国の関係性」です。①と②の歴史の流れは別々ですが、実は「つながっている部分」があります。
具体的な例を挙げると…
▶16世紀の宗教改革でヨーロッパでの布教活動が難しくなったカトリック教会が布教活動のためアジアに進出→ザビエルが鹿児島にキリスト教を伝える(1549年)
(ザビエルが来航した時期から宗教改革が起こった時期がある程度つかめる)
▶1858年の日本とアメリカの間で日米修好通商条約が結ばれ、貿易が始まる→アメリカで南北戦争が起こる(1861~65年)→当時の日本の最大貿易相手国はイギリス
(※幕末に外国でどんなことが起こっていたのかがある程度つかめる)といった感じです。
こうした「つながり(時間軸)」をいくつかおさえておくことが、今後、入試問題を解いていくときに役立ちます。意識しておさえるようにしましょう。
(歴史3)あれば便利!学習効果を高める歴史の教材
| 教材 |
説明 |
| 用語集 |
「歴史用語の意味」や「起こった出来事の内容」、「歴史上の人物が行ったこと」などを詳しく理解するために使用。
用語の補足説明を通じて「時代ごとの内容の理解を深める教材」です。 |
| 年表 |
「時代ごとの特徴」や「他の地域との時間軸のつながり」を把握するために使用。
年表から「時代の大きな流れや他地域との関連性をつかむ教材」です。 |
| 資料集 |
「時代ごとの社会のしくみ、時代の移り変わり」を「地図や歴史資料、図版など」を通じて理解するために使用。
用語の補足説明・地図・歴史資料などをもとに「歴史上できごとと、その前後のつながりを同時につかむ力を養う教材」です。 |
※用語集が「用語の説明がメイン」、年表が「年号+時代の特徴がメイン」であるのに対して、資料集は「用語の説明・年表・地図・写真・図版(グラフなど)」がバランスよくまとめられたものが多く、使い勝手が良いです。
[用語集のおすすめ]
「詳説 用語&資料集 社会3600」(受験研究社)
※地歴公が1セット
[参考書のおすすめ]
「くわしい中学歴史」(文英堂)
[資料集のおすすめ]
「アドバンス 中学歴史資料」(帝国書院)
※学校で購入・配布されているものがある場合は、そちらを使用しましょう!
(公民1)「用語の習得」や「しくみの理解」を最優先に!
![]()
公民の学習内容における「地理・歴史」との違いは、ズバリ「知らない用語が多いこと」と「しくみが複雑で分かりにくいこと」です。この科目を攻略する方法の第1歩は、「用語を知ること(暗記)」と「しくみを理解すること」です。
地理・歴史で説明してきたこととは全く逆に聞こえるかもしれません。ただ、公民に関しては、まず用語を覚え、しくみを理解しないことには何も始まりません。なので、まずは徹底的に用語の習得やしくみの理解に努めるようにしましょう。
ある程度、用語の習得やしくみの理解が進んでくると、用語やしくみに関する問題の半分以上は正答できるようになってきます。間違ってしまった「知らない用語」や「理解が不十分なしくみ」は、そのときにおさえる感じで構いません。とにかく短時間で何度も問題演習を繰り返すことで正答できる問題を確実に増やし、定着させましょう。
※「公民」は学ぶ内容から「①現代社会(現在の社会の様子・世の中のルールを知る)」「②政治のしくみ(問題を解決する方法を知る)」「③経済のしくみ(お金のはたらきを知る)」「④国際社会(他の国とのつきあい方を知る)」の4つに分類できます。
用語やしくみに難しさを感じた場合は、「日常の生活の中のどの部分の話なのか」イメージしてみてください。選挙権など、まだ持ち合わせていないイメージもあるでしょうが、見たことがあるもの、聞いたことがあるものに結びつけることができれば、一気に理解度が上がります。
(公民2)テーマ学習段階で応用問題にも取り組もう!
問題集などで「用語やしくみに関する一問一答形式の問題」が7~8割できるようになったら、次は資料をもとに「内容を説明する問題」、「正誤を判断する問題」、「理由を説明する問題」に取り組んでみてください。最初のうちは、教科書やテキストに書かれているもの(見たことのあるもの)をそのまま解答するタイプが多いため、割と解きやすく感じるはずです。
しかし、入試問題のような「はじめて見る資料をもとに、その場で考えて解答する」問題に取り組む段階になると、解きにくさや苦手意識を感じる生徒も出てきます。知識はあっても、問題の指示に従って解答をまとめる(思考する・記述する)ことに不慣れで「時間内に解答をうまくまとめられない」のです。
こうした国語関係の能力は、入試直前の対策だけで何とかなるような性質のものではありません。また、あらためて認識しておいてもらいたいのが、公民分野は、中学校3年間の最後に学ぶ科目であり、地理や歴史ほど十分な復習時間を確保することが難しい(応用問題対策の時間を考えるとなおさら)ということです。
そこで、公民分野の受験勉強法に関しては、「学習するテーマごとに必ず応用問題にも取り組むこと」をおすすめします。学習したばかりのタイミングで正答できなくても構いません。大切なのは「入試で何が問われているか」と「問題を解く上でどんな力が必要なのか」を知ることです。その後の学習で「資料の読み取り方」や「問題が問うている内容の正確な理解」「解答のまとめ方」(=解答のしかた)が見えてくると、得点力が大きく上がっていきます。
「いつまでに」「何を」「どういうふうに」勉強するか
![]()
基本の考え方が分かれば、推察できるようになる!
世界地理の問題で次のような出題があったとします。( できれば問題の解答と、選んだ理由(根拠)を頭の中で用意した上で先に進むようにしてください。 )
〈問〉次の表はコーヒー豆とカカオ豆の世界での生産量上位5カ国を表しています。
表中で空欄になっている3位にはどちらも同じ国が入ります。この国にあてはまる国として適切なものを、次のア~エから1つ選んで記号で答えなさい。
![【コーヒー豆とカカオ豆の世界での生産量上位5カ国】]()
この問題の正答に至るアプローチとしては、「農産物の生産に関する資料を丸暗記すること」が挙げられますが、そのやり方だと、すべて農産物について暗記しておかないと解けないことになってしまいます。この問題のポイントは「農産物の生育環境を理解しているか(読み取れているか)どうか」です。コーヒー豆もカカオ豆も熱帯地域の農産物です。
このことは生産量の多いブラジル・ベトナム・コートジボワール・ガーナの「地球上の位置」から推察することもできます。この考えをもとにして選択肢の中から「同じような位置(赤道付近)にある国」を選ぶと …「ウ」のインドネシアということになります。
「丸暗記がよくない」というわけではありません。「基本の考え方をマスターすること」は「正答に至るアプローチ方法を複数持つこと」につながり、結果として「解ける問題が増える=得点力が上がる」ことが大切なのです。
このことは歴史でも同じです。「1883年に大阪紡績所を開業した中心人物は誰ですか?」と問われたとします。誰なのか知識として暗記したことがなかったとしても、「その時代の人物で、そんなことができるような人は誰だろう?」「知っている人の中であり得るとしたら…」と考えると、「渋沢栄一」を引っ張り出せるのです。
もちろん間違ってしまうこともあるわけですが、考えなしに適当な人物を記入したり、解答欄を空白にしたりせずに、こういう論理的なアプローチを心がけ、習慣にしましょう。推察した答えが正解だったときはそのまま知識として取り込み、間違いになったときは、きちんと復習してアプローチのしかたを修正すればいいのです。
受験準備は、取り組みやすい「日本地理」から始めよう!
社会の学習は「世界地理」「日本地理」「歴史前半(幕末まで)」「歴史後半(明治維新以降)」「公民(現代社会・政治分野)」「公民(経済分野・国際社会)」の6つに分類できます。
このうち、中学生が1人でも学習を進めやすいのは「日本地理」と「歴史前半」です。特に「日本地理」は、もともと知っている内容が多いことに加えて2年生の冬休みあたりには習い終わっている中学校も多いことから、最も取り組みやすいテーマと言えます。
習い始めの段階から「基本~標準問題レベルは2年生のうちに仕上げる」つもりで積極的に取り組んでおくと、3年生になったときに「①実力テストで日本地理を得点源にできる」「②社会の復習時間にゆとりができるので、その分を3年生で学習内容が難化する英語や数学に回せる」といった大きなアドバンテージを得られます。
また、日本地理分野の応用問題対策に時間をかける意味でも、早い段階で日本地理の基礎固めをしておくことはとても有効です。
3年生になったら「どこで」「何を」勉強するかを明確にしよう!
3年生になると、学校行事や部活などで日々の生活がますます忙しくなり、ぼんやりしているとすぐに時間が過ぎ去ってしまいます。限られた勉強時間を有効活用するためにも、ここで学習方針をはっきりさせておくようにしましょう。
例を挙げると、まず4月段階で中学校が「歴史後半」を進めているなら、「歴史後半」は、学校(+集団塾、または個別指導塾など)中心で仕上げると決めます。また、同時に、自宅(自主学習)中心で、「歴史前半」を仕上げると決め、それぞれの場所での学習に集中して取り組むようにします。(この部分が曖昧になると、そのしわ寄せがすべて夏休みの負担としてのしかかることになります)
このように学習計画を立てて、ある程度学習が進捗していると、できていない部分があったとしても「どの部分をやり残しているか」が分かっているので、夏休み段階で先述した6つのテーマごとにバランスよく学習の時間配分をすることが可能です。
夏休み明けには志望校を決める基準となる模試や学校の実力試験が控えているので、このタイミングで学習した範囲までの総仕上げ(1回目)を行うようにしてください。3年生になっても何となくしか勉強してこなかった人や、夏休みからしか勉強していない人に大きな差をつけることができるでしょう。
テストは最高の復習教材!やり直しを通じて得点力を高めよう!
みなさんは普段からテストのやり直しをきちんとやっているでしょうか? 社会では、「次々と新しい問題に取り組むこと」よりも「過去に正解できなかった問題を克服すること」が一番の得点アップにつながります。
ただ、やり直しと言っても、間違った問題をすべてやり直すわけではありません。解けるはず(=得点にできていたはず)だった問題を「狙い撃ち」でやり直すのがコツです。
例を挙げると、①「見たことや聞いたことはあったけど忘れてしまったこと、他の知識と混ぜこぜになっていたこと」を整理して憶え直す、②中途半端にしか身についていなかった「解き方や考え方(問題へのアプローチ方法)」を再確認する(時間内でできるようにする)、③「受験校の出題傾向」に合わせて短時間で多くの設問をこなす練習をする(学習経験値を高める)、といった感じです。