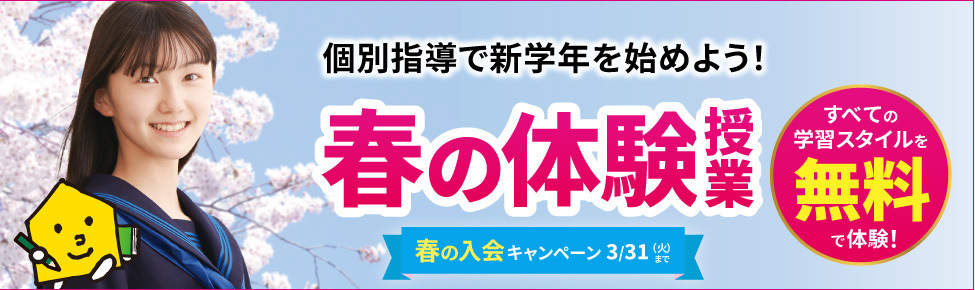学力検査では、中学校で習ったことをどれだけ理解しているかが試されます。最近は、知識だけでなく「思考力・判断力・表現力」が重視され、「資料の読み取り」や「自分の考えや結果に至った理由を述べる」といった、覚えた知識を活用する問題が多くなっています。こうした入試問題の出題傾向を知っておくことで、受験勉強で必要な対策がわかります。
英語
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数・小問数は昨年と変化がありませんでした。今までは「聞く・話す・読む・書く」の4領域でしたが、「話す」が「発表」と「やり取り」に細分化され、より総合的な能力をみられるような形式になりました。具体的な変化としては、リスニングでの英単語の記述がなくなったり、英問英答が復活したりと細かな変更が多くなされました。また、難解な文章表現も多かったことから、昨年よりも難しくなったと思われます。 平均点は56.4点→47.1点と大きく下降しました。
対策のポイント
長文読解が50点分!
長文読解は、大問7が資料の読解、大問8が物語文、大問9が会話文となるのが例年です。長文は速く読まなければいけないと考えがちですが、ゆっくり読んでも正確な訳がとれない状態で焦って長文を読もうとしても点数は伸びません。まずは、基礎となる英単語と文法の力をじっくり身につけましょう。
英作文は10単語程度!
2025年は、2コマのイラストから会話の流れに合うように10語程度で記述する問題が2題出題されました。これは昨年度と同じ傾向です。英文は2文になっても問題なく、難しい英文を記述する必要はないので、できるだけ簡単な文法や単語で解答するようにし、ミスがないかを注意しましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスニング | 正しい答えを選ぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 絵や地図を使う | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メモ・グラフ・表を完成する | − | − | − | − | |
| 日本語[英語]で答える | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 自分の考えを英語で書く | − | − | − | − | |
| 発音・アクセント | 発音・アクセント | − | − | − | − |
| くぎり・強勢・抑揚 | − | − | − | − | |
| 読解 | 英文和訳(記述) | − | − | − | − |
| 脱文挿入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 要旨把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句解釈 | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文整序 | − | − | − | − | |
| 指示語 | − | − | − | − | |
| 会話文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文法・英作文 | 和文英訳 | − | − | − | − |
| 単語の穴埋め | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 正誤問題 | − | − | − | − | |
| 言い換え・書き換え | − | − | − | − | |
| 英問英答 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 条件英作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自由英作文 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 小問数 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| リスニング | 11 | 11 | 9 | 9 |
| 英作文 | 2 | 3 | 3 | 3 |
数学
2026年度/令和8年度
出題傾向
全体の構成については昨年と変化がありませんでした。ただ、大問4については規則性が頻出傾向にあったところ、昨年から変化の兆しが見られ、今年は図形の複合問題となりました。これにより、大問1と3も含めた図形問題の割合が増え、合計で40点分にもなりました。 大問1の小問集合は51点分の配点ではあるものの、空間図形や確率では正答率が30%以下の難問も混ざっています。全体の難易度としては昨年とほぼ変化がなく、平均点は51.9点→52.0点と僅かに上昇しました。 数学ではマークシート化により、マークミスでの失点が懸念されています。しっかりと見直しをするようにしましょう。
対策のポイント
出題のパターンが決まっている!
図形の証明や作図など、大問1~3までの内容はほぼ固定されています。そのため、自分の得意不得意を明確にしたうえで、ピンポイントで対策を行うことが可能です。定期的に模試を受けることで自分の苦手を洗い出しましょう。また、大問1には基礎的な計算問題がまとまっているので、必ず解けるようにしましょう。
各大問の最終問題は難しい!
2025年の大問2~4の最終問題の正答率は、それぞれ5.5%、2.0%、12.6%でした。大問4に関しては、2年連続でパターンが変わっていることもあり、難易度は他の大問に比べてやや易しめです。時間を使うなら大問4に使ってみるとよいかもしれません。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数と式 | 正負の数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 文字式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 方程式・不等式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 式の計算 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 連立方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平方根 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 多項式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2次方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 | 比例と反比例 | − | ◯ | − | ◯ |
| 1次関数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 y = ax2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 図形 | 平面図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 空間図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平面図形と平行線の性質 | − | − | − | ◯ | |
| 図形の合同 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 図形の相似 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 円周角と中心角 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 三平方の定理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| データの活用 | データの分布・比較 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 確率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 標本調査 | − | − | ◯ | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小問数 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 記述問題 | 図形の証明(説明) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の説明・証明など | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 立式・解法の過程の記述 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 作図(図形) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 作図(グラフ) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国語
2026年度/令和8年度
出題傾向
例年の配点から、聞き取りが2点減少し、古典の配点がその分増加されました。小問数も増加し、記号での解答も増加した分、記述での解答数が減少しました。マークシート化の影響で記述問題と記号問題の数がほぼ逆転し、記号問題が占める割合の方が多くなりました。一方で、正答率の低かった問題が記述問題に集中していることから、今年度の対策としては記述問題に力を入れてみると周囲と差がつくれる要因になり得ると予想できます。 平均点は50.4点→56.6点と大きく上昇しました。
対策のポイント
1・2年生の間から長期的な視点を!
国語は、偏差値を上げるのに最も時間のかかる科目だと思ってください。漢字の読み書きや文法といった比較的対策のしやすい単元は、約20点と決して高くはありません。逆に各種読解問題や聞き取り、作文は残りの80点分を占めています。"国語力"は一朝一夕では身につきません。長期的な目で見て対策をしてください。
作文は必ず他者に採点してもらおう!
作文は誤字脱字をしたら-1点、具体例がなかったら-4点、一定の字数未満は採点対象とされないなど細かいルールが数多く決まっています。まずはルールを守って減点されないようにしましょう。また、解答として成立しているかどうかは自分自身では判断しづらいため、塾の先生や保護者など身近な大人にお願いするようにしましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢字・語句 | 漢字(読み・書き・筆順・画数・部首) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 熟語(三字熟語・四字熟語) | − | − | − | − | |
| 語句(ことわざ・慣用句) | − | − | − | − | |
| 文法 | 文と文節 | − | − | − | − |
| 品詞・用法 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 敬語、その他 | − | − | − | − | |
| 表現・情報 | グラフ・図表の読み取り | − | ◯ | − | − |
| 話し合い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 伝え方の工夫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 課題作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聞き取り問題 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学史 | 文学史 | − | − | − | − |
| 現代文(読解) | 主題・表題 | − | − | − | ◯ |
| 大意・要旨 | − | − | − | − | |
| 情景・心情 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文脈把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文章構成 | − | − | − | − | |
| 指示語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 接続語 | − | − | − | − | |
| 脱文・脱語補充 | − | − | − | − | |
| 古典 | 古文のかなづかい・古語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 古文の会話・主語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 古文の展開 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文章のジャンル | 論説文・説明文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 記録文・報告文 | − | − | − | − | |
| 小説・伝記 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 随筆・紀行・日記 | − | − | − | − | |
| 詩 | − | − | − | − | |
| 和歌(短歌) | − | − | − | − | |
| 俳句・川柳 | − | − | − | − | |
| 古文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 小問数 | 32 | 33 | 33 | 35 |
| 記号解答 | 12 | 14 | 19 | 22 |
| 記述式解答(漢字の読み書きも含む) | 20 | 19 | 14 | 13 |
理科
2026年度/令和8年度
出題傾向
2025年は大きな傾向の変化がありました。まず、用語の記述が一切なくなりました。さらに、計算問題や作図の割合が増加し、問題のページも1枚追加されました。用語の暗記や問題パターンに慣れていれば点数に繋がる問題が多かった状況から、思考力や表現力を問われる問題が多くなったのが特徴です。 物理と地学の領域の正答率が40%台なのに対して、化学と生物の領域は60%台と領域によって大きな差がありました。全体的な難易度としては依然として難化の傾向にあり、平均点は59.1点→55.4点と昨年に引き続き下降しました。
対策のポイント
苦手分野をつくらないこと!
理科では、3年間で学習する内容から幅広く出題されるため、1~3年生の内容に穴がないことが重要です。数学や英語とは違い、一度習った単元が次の定期テストで出題されることも少ないので、過去の単元を忘れてしまっている場合が多いことでしょう。理科を得意科目にする秘訣は、毎回の定期テストでしっかりと勉強して、模試や受験の時期に思い出しやすい状態を作っておくことにあります。日々の積み重ねを大切にしましょう。
各分野の対策方法
生物的・地学的領域:暗記が中心です。まずは語呂合わせを活用して用語を確実に覚えていきましょう。また、実験のレポートが出題されやすいため「なにを調べる実験なのか」「どういう条件を設定すればよいか」など記述問題にも備えましょう。 化学的・物理的領域:暗記・計算どちらも出題されます。化学変化や電気の単元は出題頻度が高いので注意しましょう。計算問題のパターンは決して多くないので、模試や過去問演習でいろいろな問題に挑戦しておきましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 力のはたらき | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| 光と音 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 電流 | ◯ | − | ◯ | − | |
| 電流と磁界 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 力のつり合いと合成、分解 | − | − | ◯ | − | |
| 運動の規則性 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 仕事とエネルギー | ◯ | − | − | ◯ | |
| 化学 | 物質のすがた | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 水溶液 | − | ◯ | − | ||
| 状態変化 | ◯ | − | − | ◯ | |
| 物質の成り立ち、原子・分子 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 物質の化学変化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 化学変化と物質の質量 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 水溶液とイオン、電池とイオン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 化学変化と電池 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生物 | 生物の観察と分類の仕方 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生物の体の共通点と相違点 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 生物と細胞 | − | ◯ | − | − | |
| 植物の体のつくりと働き | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 動物の体のつくりと働き | ◯ | ◯ | − | − | |
| 生物の成長とふえ方 | ◯ | − | − | − | |
| 遺伝の規則性と遺伝子 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 生物の種類の多様性と進化 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 地学 | 身近な地形や地層、岩石の観察 | − | ◯ | ◯ | ◯ |
| 地層の重なりと過去の様子 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 火山と地震 | ◯ | − | − | − | |
| 自然の恵みと火山災害・地震災害 | ◯ | − | − | − | |
| 気象観測 | − | − | − | − | |
| 天気の変化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 日本の気象 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自然の恵みと気象災害 | − | − | − | − | |
| 天体の動きと地球の自転・公転 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 太陽系と恒星 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 分野融合 | エネルギーと物質(物理・化学) | − | − | − | − |
| 自然環境の保全と科学技術の利用(化学・生物) | − | − | − | − | |
| 生物と環境(生物・地学) | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 小問数 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 記号解答 | 16 | 17 | 22 | 27 |
| 短文記述 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 計算問題 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 図・グラフ、モデル | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 語句記述 |
社会
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問は1~8までで、例年と変化はありませんでした。小問数や配点についても例年から大きく変わっていません。しかし、記号解答数が24問→27問とやや増加し、用語記述回答数が5問→1問と大きく減少しました。 地理・歴史分野からは大問2つずつ、公民からは3つ出題されます。一見、公民分野の割合が大きいように見えますが、配点が一番低いことに注意しましょう。各分野において、基礎的な知識を問う問題と社会的事象についての思考・表現力を見る問題が出題されています。平均点は57.5点→51.7点と下降しました。
対策のポイント
千葉県を題材にした総合問題が出題!
ここ数年は、大問1で千葉県を題材にした資料の読み取りと3分野の総合問題が出題されます。千葉県内の市の配置や成田国際空港、チバニアンについてなど予備知識を入れておきましょう。過去問や模試を活用できるとよりよい対策となります。
ただの暗記科目にならないように!
社会は、全大問を通して資料の読み取り問題が中心となっています。暗記事項が非常に多い科目ですが、それは用語さえおさえれば社会を制する事ができるということを意味する訳ではありません。社会という科目は、全体的にボリュームがあり、尚且つそれぞれが繋がり合っているので1つの事象を様々な角度から学習することが重要です。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理的分野 | 日本の姿 世界の姿 |
地形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 気候 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 人口 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 産業・貿易 | 第一次産業(農林水産業) | ◯ | − | − | ◯ | |
| 第二次産業(工業) | − | − | − | − | ||
| 第三次産業(商業・サービス業) | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 貿易 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| 地域 | アジア州 | − | − | − | ◯ | |
| ヨーロッパ州 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| アフリカ州 | − | − | − | − | ||
| 南北アメリカ州 | ◯ | − | − | − | ||
| オセアニア州 | − | ◯ | − | − | ||
| 九州地方、中国・四国地方 | ◯ | − | ◯ | − | ||
| 近畿地方、中部地方 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 関東地方、東北地方、北海道地方 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 歴史的分野 | 日本史 | 平安時代まで | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 鎌倉・室町時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 戦国・江戸時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 明治時代以降 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 世界史 | 古代 | − | − | − | − | |
| 中世 | − | − | − | − | ||
| 近世 | − | − | − | − | ||
| 近・現代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| テーマ史 | 政治・外交史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 社会・経済史 | − | − | − | − | ||
| 文化史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 公民的分野 | 政治 | 現代社会と私たちの生活 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 個人の尊重と日本国憲法 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 現代の民主政治、三権分立 | − | − | − | ◯ | ||
| 地方自治 | − | − | − | − | ||
| 経済 | 消費生活と流通 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 企業と生産活動 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 財政、国民生活と福祉 | − | − | − | − | ||
| 国際 | 地球社会と私たち | − | − | − | − | |
| 経済と貿易 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 環境問題 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 時事問題 | − | − | − | − | ||
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 小問数 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| 記号解答 | 19 | 20 | 24 | 27 |
| 用語記述 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| 文章記述 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 作業・作図 | 0 | 0 | 0 | 0 |