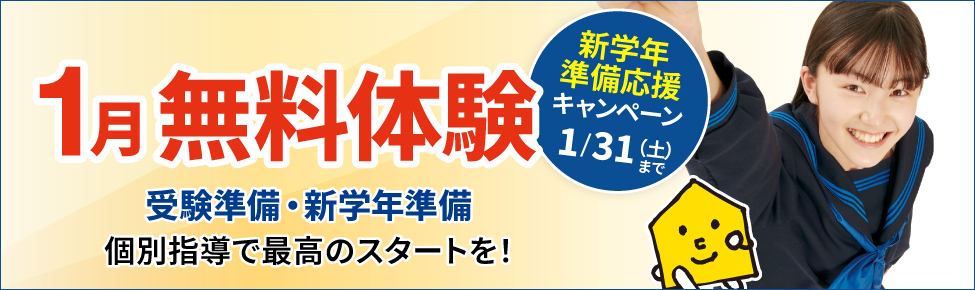学力検査では、中学校で習ったことをどれだけ理解しているかが試されます。最近は、知識だけでなく「思考力・判断力・表現力」が重視され、「資料の読み取り」や「自分の考えや結果に至った理由を述べる」といった、覚えた知識を活用する問題が多くなっています。こうした入試問題の出題傾向を知っておくことで、受験勉強で必要な対策がわかります。
英語
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数は4問で、例年どおり大問1がリスニング、大問2で会話文など、大問3・4で資料読解・長文の構成となっています。大量に問題を解くよりも、資料・英文をしっかり読解することを重視しています。リスニングの配点は20点で、他県と比較して配点は低めなのが特徴ですが、放送が1度しか流れない問題が導入されるなど難度は年々上がってきています。なお定期テストや普段の授業では頻出の「和訳」や語句整序、アクセント問題はほぼ出題されないのも特徴ですが、これは大学入試のトレンドを踏襲したものといえます。
対策のポイント
日常生活に密着した資料・文章に触れよう
「イベント告知の案内」や「地域のお祭りの紹介」など、日常、見たり体験したりする事柄をテーマとした出題が増えています。英語の枠にとらわれず、ふだん目にするお便りにはどんなことが書いてあるのだろうとか、何かを人に紹介するとしたら自分ならどんな構成にするだろう、といったことを意識するのも大事な対策です。
会話文に慣れよう
大問2では毎年、場面にふさわしい会話を完成させる「会話文」の出題があります。近年では大問3や大問4の読解問題の中にも、文の流れに合う語句を書いたり選んだりする出題が出てきました。ポイントは『相手の質問の文の形(be動詞・一般動詞や疑問詞など)』をしっかりととらえることです。類題で慣れていきましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスニング | 正しい答えを選ぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 絵や地図を使う | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メモ・グラフ・表を完成する | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 日本語[英語]で答える | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自分の考えを英語で書く | − | − | − | − | |
| 発音・アクセント | 発音・アクセント | − | − | − | − |
| くぎり・強勢・抑揚 | − | − | − | − | |
| 読解 | 英文和訳(記述) | − | ◯ | − | − |
| 脱文挿入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 要旨把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句解釈 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指示語 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 会話文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文法・英作文 | 和文英訳 | − | ◯ | ◯ | − |
| 単語の穴埋め | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句整序 | − | − | − | − | |
| 正誤問題 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 言い換え・書き換え | − | − | − | ◯ | |
| 英問英答 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 条件英作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自由英作文 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 小問数 | 38 | 38 | 35 | 35 |
| リスニング | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 英作文 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数学
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数は4、小問数は36とほぼ例年どおりの構成。大問2は、Ⅰで「資料の活用」が定着しましたが、Ⅱは数の規則性や方程式などテーマは年によって流動的です。大問4では相似の証明が昨年に引き続き出題。また今年は一次関数の解き方(過程)を記す設問が2題あり、解に至った過程を言語化する力が求められます。例年、数と式・関数や図形・データの活用が満遍なく出題されているため分野ごとバランスよく対策したいですが、長野の入試は時間がタイトなので、速く解く練習はもちろん問題を取捨選択して効率よく得点する戦略も必要です。
対策のポイント
大問1でしっかり得点しよう
大問1はいわゆる「小問集合」で、作図や連立方程式・関数も含めて広い分野からの基礎的な問題が並びます。長野県の数学は問題量の割に解答時間が十分とは言えないため、応用問題ばかりに目を向けず、例年36点分と大きな比重を占める大問1をまずは確実に得点することから始めましょう。
関数の文章題は繰り返し練習しよう
例年、関数の文章題と、関数に図形を絡めた計算問題が出題されます。文章題ではグラフも一緒に示されるので、丁寧に文章を区切って、グラフが文章中のどの場面を示しているのかをつかむ練習をしましょう。解法のパターンを身につけるため、同じ問題を繰り返し解くのも有効です。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数と式 | 正負の数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 文字式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 方程式・不等式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 式の計算 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 連立方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平方根 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 多項式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2次方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 | 比例と反比例 | ◯ | − | ◯ | ◯ |
| 1次関数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 y = ax2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 図形 | 平面図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 空間図形 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 平面図形と平行線の性質 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 図形の合同 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 図形の相似 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 円周角と中心角 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 三平方の定理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| データの活用 | データの分布・比較 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 確率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 標本調査 | ◯ | ◯ | ◯ | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小問数 | 36 | 36 | 35 | 36 | |
| 記述問題 | 図形の証明(説明) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| その他の説明・証明など | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 立式・解法の過程の記述 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 作図(図形) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 作図(グラフ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国語
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問5までの構成・内容ともに例年通りで、漢字・文法、文章読解、古典と、幅広くバランスのよい配分です。数学と同様、試験時間に対しての問題量が多いため、全体として時間との闘いになったと思われます。例年大問2で「学級会での話し合いの場面」をもとにした設問があり、そこでは『他者の発言に耳を傾け、考えること』の大切さが問われています。他者との関わりを重視した出題傾向は今後も続くでしょう。また今年は、昨年はなかった漢文が出題。知識そのものを問うのではなく、やはり生徒の話し合いと絡めた設問になっています。
対策のポイント
60字〜90字程度の作文を練習しよう
長野県の国語入試は「作文」が単独では出題されず、代わりに60字〜90字程度の記述が3問ほど課されるという全国的にも珍しい出題形式です。200字程度ある作文や30字程度の記述と比べ、これくらいの字数の文章が最も書きづらいです。ふだんから字数を意識するために、長めの文章を要約する練習をしてみましょう。
まんべんなく知識を確認しよう
長野の国語は、極端な難問はなく幅広い知識と理解を少しずつ問うてくる形です。したがって、読解力だけを意識するのではなく文法・敬語、漢字・熟語や古語の歴史的かなづかいなど、細かな項目を丁寧に学習することがそのまま得点につながります。文中の誤字を指摘する設問も毎年出ていますので、注意深い観察力も必要です。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢字・語句 | 漢字(読み・書き・筆順・画数・部首) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 熟語(三字熟語・四字熟語) | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 語句(ことわざ・慣用句) | − | − | ◯ | − | |
| 文法 | 文と文節 | − | − | − | − |
| 品詞・用法 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 敬語、その他 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 表現・情報 | グラフ・図表の読み取り | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| 話し合い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 伝え方の工夫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 課題作文 | − | − | − | − | |
| 聞き取り問題 | − | − | − | − | |
| 文学史 | 文学史 | − | − | − | − |
| 現代文(読解) | 主題・表題 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大意・要旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 情景・心情 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文脈把握 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 段落・文章構成 | ◯ | − | ◯ | − | |
| 指示語 | − | ◯ | − | − | |
| 接続語 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 脱文・脱語補充 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 古典 | 古文のかなづかい・古語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 古文の会話・主語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 古文の展開 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 文章のジャンル | 論説文・説明文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 記録文・報告文 | − | − | − | − | |
| 小説・伝記 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 随筆・紀行・日記 | − | − | − | − | |
| 詩 | − | − | − | − | |
| 和歌(短歌) | − | − | − | − | |
| 俳句・川柳 | − | − | − | − | |
| 古文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | − | ◯ | − | ◯ |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 39 | 41 | 35 | 35 |
| 記号解答 | 12 | 18 | 13 | 12 |
| 記述式解答(漢字の読み書きも含む) | 26 | 23 | 22 | 23 |
理科
2026年度/令和8年度
出題傾向
生物・化学・地学・物理それぞれの大問計4題は変更がありませんでしたが、全体の小問数が昨年から3問増え、記述・論述問題は5問増えています。昨年は問題数が減った分、思考力が試された出題でしたが、今年は設問数が一昨年までの分量に戻りつつあり、また昨年と比べ、日常生活の現象に絡めた独自問題よりも教科書の典型的な実験や観察の問題が顕著だったことからも、理科の基本知識や素養の重視への回帰が見えます。生物分野の観察問題、化学分野の水溶液・物質のすがた・化学変化は4年連続出題されているため、特に対策が必要です。
対策のポイント
実験や観察を、自分なりにもう一度まとめよう
長野の入試問題は、教科書に載っている実験・観察の図や手順そのままではなく、違う切り口で構成して出題することもまだ多いので、資料集・教科書の暗記では対応が難しくなっています。したがって典型的な実験については、目的・方法・予想・結果を自分のことばでまとめ直し、原理・原則をとらえる練習をしていきましょう。
現象(結果)と理由の両方を書けるようにしよう
一昨年までの入試の記述問題はほとんどが「理由(~から。)」を問うものだったのに対し、昨年から「現象(~になる。)」を記述するものが多くなっています。答えるべき内容をこのように年によって変えてくることもあるので、記述問題の練習では「現象(結果)」と「その理由」をそれぞれ表現する習慣を付けましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 力のはたらき | ◯ | − | ◯ | ◯ |
| 光と音 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 電流 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 電流と磁界 | ◯ | − | − | − | |
| 力のつり合いと合成、分解 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 運動の規則性 | ◯ | − | − | − | |
| 仕事とエネルギー | − | − | − | − | |
| 化学 | 物質のすがた | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 水溶液 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 状態変化 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 物質の成り立ち、原子・分子 | ◯ | − | ◯ | ||
| 物質の化学変化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 化学変化と物質の質量 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 水溶液とイオン、電池とイオン | − | ◯ | − | − | |
| 化学変化と電池 | − | − | − | − | |
| 生物 | 生物の観察と分類の仕方 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生物の体の共通点と相違点 | − | − | − | − | |
| 生物と細胞 | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 植物の体のつくりと働き | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 動物の体のつくりと働き | − | ◯ | − | − | |
| 生物の成長とふえ方 | − | − | − | ◯ | |
| 遺伝の規則性と遺伝子 | − | − | − | ◯ | |
| 生物の種類の多様性と進化 | ◯ | − | ◯ | − | |
| 地学 | 身近な地形や地層、岩石の観察 | − | − | ◯ | ◯ |
| 地層の重なりと過去の様子 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 火山と地震 | ◯ | − | − | − | |
| 自然の恵みと火山災害・地震災害 | − | − | − | − | |
| 気象観測 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 天気の変化 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 日本の気象 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 自然の恵みと気象災害 | − | − | − | − | |
| 天体の動きと地球の自転・公転 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 太陽系と恒星 | − | − | − | ||
| 分野融合 | エネルギーと物質(物理・化学) | − | − | ◯ | ◯ |
| 自然環境の保全と科学技術の利用(化学・生物) | − | − | − | − | |
| 生物と環境(生物・地学) | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 小問数 | 39 | 42 | 35 | 38 |
| 記号解答 | 15 | 20 | 14 | 15 |
| 短文記述 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 計算問題 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 図・グラフ、モデル | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 語句記述 |
社会
2026年度/令和8年度
出題傾向
今年も歴史・地理・公民それぞれの大問、計3題でした。配点の上では、歴史分野の比重が少なく、地理・公民を重視する傾向も例年どおり。全体的に、単問単答ではなくひとつの問いに対して複数の資料を参照して答える設問が多いため、資料に惑わされて正解を導きにくいこともあります。特筆される変化は、ここ2年出題されていた日本国憲法や国政に関しての出題はなく、地方自治や私たちの暮らしに関連する問題が多かったことです。例年大問3は、5~6個の統計やグラフを同時に検討して見解を述べるもので、思考力と判断力が問われます。
対策のポイント
資料や言葉にマークをする習慣をつけよう
長野の入試は1ページに込められた文字数や資料数が非常に多いため、慣れないと指定された資料のありかを見つけられず、時間を損失することがあります。正しく目を配るために、ふだんから問題を解くときには例えば「資料1」とあったら大きく丸で囲んで資料と矢印でつなぐなど、目立つ工夫をしてミスを防ぎましょう。
記述問題は模範解答を参考にしよう
複数の資料の情報を組み合わせて答えるオリジナル問題が大半なため、教科書には載っていない解答が多いです。過去問や学校の総合テストの復習の際は、模範解答を見て、この部分は資料1、ここは資料2、というように、資料が記述のどこに盛り込まれているのかを確認するクセをつけましょう。記述のコツがつかめるはずです。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理的分野 | 日本の姿 世界の姿 |
地形 | ◯ | − | ◯ | ◯ |
| 気候 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 人口 | ◯ | ◯ | − | − | ||
| 産業・貿易 | 第一次産業(農林水産業) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 第二次産業(工業) | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 第三次産業(商業・サービス業) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 貿易 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 地域 | アジア州 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| ヨーロッパ州 | − | − | − | ◯ | ||
| アフリカ州 | − | − | − | − | ||
| 南北アメリカ州 | ◯ | ◯ | − | ◯ | ||
| オセアニア州 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| 九州地方、中国・四国地方 | − | − | ◯ | − | ||
| 近畿地方、中部地方 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| 関東地方、東北地方、北海道地方 | ◯ | ◯ | − | − | ||
| 歴史的分野 | 日本史 | 平安時代まで | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 鎌倉・室町時代 | ◯ | ◯ | ◯ | − | ||
| 戦国・江戸時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 明治時代以降 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 世界史 | 古代 | − | − | − | − | |
| 中世 | − | − | − | − | ||
| 近世 | − | − | − | − | ||
| 近・現代 | − | − | − | ◯ | ||
| テーマ史 | 政治・外交史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 社会・経済史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 文化史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 公民的分野 | 政治 | 現代社会と私たちの生活 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 個人の尊重と日本国憲法 | − | ◯ | ◯ | − | ||
| 現代の民主政治、三権分立 | − | ◯ | ◯ | − | ||
| 地方自治 | − | − | − | ◯ | ||
| 経済 | 消費生活と流通 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 企業と生産活動 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 財政、国民生活と福祉 | ◯ | ◯ | − | ◯ | ||
| 国際 | 地球社会と私たち | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 経済と貿易 | ◯ | − | − | − | ||
| 環境問題 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 時事問題 | ◯ | − | − | ◯ | ||
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 小問数 | 39 | 38 | 35 | 37 |
| 記号解答 | 16 | 21 | 18 | 23 |
| 用語記述 | 5 | 11 | 9 | 7 |
| 文章記述 | 11 | 11 | 9 | 8 |
| 作業・作図 | 0 | 0 | 0 | 0 |