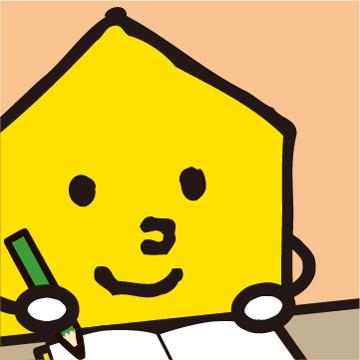所在地
〒646-0027 田辺市朝日ヶ丘18-4朝日ヶ丘ダイケンビル2階東アクセス
田辺保健所西向かい ダイケンビル2F
駐車場 : 建物入口前にある駐車スペースをご利用ください。
駐輪場 : 校舎向かいにある初山さんの駐輪場をご利用ください。
まっすぐ進むと右手にアクシス田辺校が見えてきます。
右側の入り口から階段のぼって2階が受付です。
反対側から見ると、西牟婁総合庁舎(田辺保健所)の西向かいになります。
通常授業時間帯
※講座により、開校曜日・時間帯が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
コース例
小1〜6
田辺東部小・会津小・田辺第二小など 小学校準拠コース
例:1対1個別指導(週2回)
教科書に合わせて学習を進め、中学や高校での学習の土台となる学力を育てます。わかることが増えて、勉強が楽しくなり学校の授業に積極的に参加できるようになります。
小4〜6
聞く・話す・読む・書く小学英語コース
例:ステップアップ講座(週1回)
小学校の英語は「聞く」「話す」が中心。アクシスでは、それに「読む」「書く」を加えて“使える英語力”を養成します。自分で辞書をひく練習から始めて、基本的な会話表現を学びます。
小5・6
田辺中受検コース
例:1対1個別指導(週3回)
適性検査という出題形式に慣れ、図や表から題意を汲み取って、自分の考えで表現できる力を養います。小学校の学習内容について、基礎的な演習を強化して学習します。
小3〜6
智辯中・近大附属中・開智中など私立中受験コース
例:Axisのオンライン家庭教師(週3回)
答えを導き出す過程を大切にして、先生との対話の中で自分の考えを表現する練習を重ねます。受験期には過去問で出題パターンに慣れ、スピードと正確さを身につけます。
小1〜6
国語・算数基礎学力養成コース
例:ステップアップ講座(週2回)
無学年制のオリジナル教材を使用します。計算力と漢字力、文章を読む力を正しい学習方法でしっかり身につけ、算数の文章題や図形問題、国語は読解問題などにも取り組みます。
小1〜6
小1から対応!ロボットプログラミングコース
例:ロボットプログラミング講座(月2回)
プログラミングやロボット製作を通して、今後必要になる考える力や問題解決力を養います。最新の学習キット「KOOV®(クーブ)」を使って、独自のカリキュラムで学習します。
中1〜3
田辺高受験対策コース
例:オンラインゼミ(週5回)
中3の2学期には終わらせることを目標にして、オンラインゼミを活用しながら先取り学習を進めます。冬休み以降は過去問やさまざまなパターンの問題に慣れる時間を確保します。
中3
智辯高・近大附属高・開智高など 高校受験コース
例:オンラインゼミ(週3回)
オンラインゼミを活用してハイレベルな問題演習に取り組み、応用力、実戦力を養います。冬からは過去問や様々なパターンの問題になれる時間を確保します。
中1〜3
高雄中・東陽中など 中学準拠・定期試験対策コース
例:教科書準拠AI学習AxisPLUS(週3回)
中学校の教科書に準拠したカリキュラムと教材で、学校内容の先取り学習または復習をします。定期試験前には定期試験対策ゼミや勉強会・演習会により万全の対策を行います。
中1〜3
県立中・私立中 中高一貫校対策コース
例:Axisのオンライン家庭教師(週2回)
一人ひとりに合わせて学習の出発点やレベル、授業スピードを調整しながら、お通いの中学校の教科書、カリキュラム、進度に対応した学習を行います。
高2・3
和医大・和歌山大など国公立大受験コース
例:1対1個別指導(週1回)+大学受験映像講座(週2回)
志望大学、学部に応じた目標到達レベルと現在の学習状況、部活動や入試までの残り日数などの時間的な制約も考慮して優先順位を決め、個人別のプランで学習を進めます。
高2・3
関関同立・産近甲龍など私立大受験コース
例:1対1個別指導(週2回)
志望大学が明確であれば、受験可能な入試方式全てにチャレンジできる学習プランを作成します。総合型・学校推薦型選抜と一般選抜、両方の対策を確実に進めます。
高1〜3
京大・阪大・神大など難関大受験コース
例:Axisのオンライン家庭教師(週2回)+オンラインゼミ(週1回)
二次試験の出題傾向や特異な問題レベルに対応します。オンライン家庭教師のハイレベルな記述問題で合格答案を作る指導もお任せください。
高1〜3
田辺高 高校準拠・定期試験対策コース
例:Axisのオンライン家庭教師(週1回)
高校の教科書や指導内容に準拠したカリキュラムと教材で、学校内容の先取り学習または復習をします。授業後にはAxisPLUSを使ってテーマ学習の定着も図ります。学校の宿題対策も可能です。