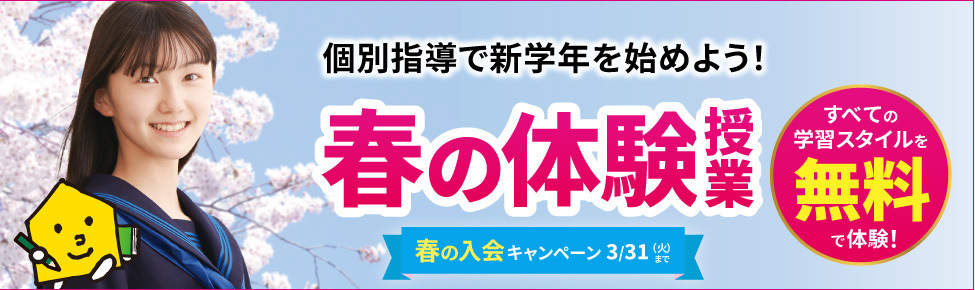崩壊の危機に瀕している?小学生の国語力
![]()
ホラー童話になってしまった「ごんぎつね」
2022年に刊行された石井光太氏の著書「ルポ 誰が国語力を殺すのか」(文春文庫)は、国語教育に携わる人の中では、衝撃とともに「悲しい共感」を生みました。
石井氏は、少年犯罪、児童虐待、不登校など、子どもたちが直面する課題を取材してきたルポライターです。その石井氏が、今起きているそれらの社会的な課題は、いまの国語教育にも原因の一端があるのではないか?と警鐘を鳴らしたのです。
その著書には、次のような「ひとつの事実」が記されていました。
とある都内の公立小学校4年生の国語の授業を見学した時のこと。その日は小学校の教科書ではおなじみの「ごんぎつね」について、みんなで意見を述べ合うグループワークが開かれていました。
<ごんぎつねのあらすじ>
ある山に、悪ふざけが好きで村人に迷惑ばかりかけている「ごん」という狐がいた。その日も、兵十という男が一生懸命獲ったうなぎや魚をわざと逃がした。
10日ばかりあと、ごんは兵十の家で葬儀を見かける。そこでごんは、兵十がうなぎや魚を獲っていたのは、病気の母親に食べさせたかったからだと気づく。その後ごんは、罪滅ぼしとして毎日山でとった栗や松茸を兵十の家に置いていく。
ある日、兵十は家に忍び込んだごんを目撃する。兵十は、またいたずらをしに来た、と火縄銃で撃ち殺した。しかし、土間に栗が置かれているのを見て、これまで食べ物を運んでくれていたのはごんだったと気づき、その場に立ちすくむ。
授業で取り上げられたのは、ごんが兵十の母親の葬儀を覗き見る場面です。家の前では村の女たちが大きな鍋で何かを煮ています。
〈よそいきの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました〉
Q.このぐずぐず煮えていたものは何か?
それが、授業の問いの一つでした。
作者・新美南吉は、きつねのごんが見た光景なので「何か」と表現しました。大人が常識的に読めば、葬式に参列する人たちへのふるまいを用意している場面だと想像できます。
ところが、子どもたちからは、まったく異なる意見が発表されたのです。
「死んだお母さんをお鍋に入れて消毒しているところだと思います」
「昔はお墓がなかったので、死んだ人は燃やす代わりにお湯で煮て骨にしていたんだと思います」
「昔は焼くところ(火葬場)がないから、お湯で溶かして骨にしてから、お墓に埋めなければならなかったんだと思います」
この学校は学力レベルとしてはごく普通の小学校だったそうです。その学校の子どもたちが、真剣にそう議論しているのです。
論理的思考力や人を思いやる情緒性が後退
私たち国語教育に携わる者は、これを単なる「ひとつの事実」として看過することはできませんでした。いまの小学生の国語力は、昔と比べると間違いなく落ちている。そしてそれが原因で、論理的な思考力や人の気持ちを察する・思いやるといった情緒性なども著しく後退している。残念ながら、それは「悲しい共感」でした。
50年で3~4割減ってしまった国語の授業
実際に調べてみると、この50年間で国語の授業は減り続けています。1968年と2020年を比べると、小学6年生で約3割、中学3年生で約4割も減っています。
【国語の授業時間数の推移
(1968年/2020年比較)】
<単位:時間>
|
1968年 |
2020年 |
増減率 |
| 小学5年生 |
245 |
175 |
-28.6% |
| 中学3年生 |
175 |
105 |
-40.0% |
(参考: 文部科学省 小学校学習指導要領)
これは、総合的な学習が増えたなど、ほかの教育目標を掲げた結果でもあり、一概に「国語教育がないがしろにされた」とは言い切れません。しかし、2022年の学習指導要領をみても、「読む力」は「心情理解」などよりも次第に「情報処理」などに重心が移っていることは明らかです。
国語力の基礎は語彙力
相手の話を理解し、自分の考えを述べて対話するコミュニケーションには、豊富な語彙力が必要です。
私たちが日常生活の中で無意識に聞き話している言葉の一つひとつは、物ごとの状態や感情・思考などを示しています。
たとえば、「今日は暑くて頭痛がするため、自分の意見がまとまらない」という一文。
「昨日」でなく「今日」。「寒い」のでも「熱い」のでもなく「暑い」ため、「頭が痛く」て集中できずに「考えがまとまらない」。
では、「暑い」と「熱い」は何が違うのでしょうか?「頭痛」という概念を知らなければ、果たして集中できない理由を相手にうまく説明できるでしょうか?「意見」とは何で、それが「まとまらない」とはどういう状況なのか? 一つひとつの言葉が持つ意味や概念を理解して、それを駆使して語ることで、相手と共通のイメージ・世界観を共有しつつコミュニケーションしています。
こうして私たちは、自分がいま持っている「語彙」を使ってものを考え、その考えを文に組み立て、書面であるいは口で語って誰かに伝えようとしているのです。
逆に言えば、思考や表現の広さや深さというのは、自分が持つ語彙の範囲を超えないのです。
10歳前後までは側頭葉、その後は前頭葉が発達
脳にはさまざまな部位とそれぞれの役割がありますが、そのなかで側頭葉は、聴覚・記憶・言語などをつかさどり、生後から10歳前後まで急速に発達します。また、前頭葉は、人格・社会性・思考力をつかさどり、小学校中学年ごろから急速に発達していくそうです。
【側頭葉/前頭葉の成長と関わる能力の成長曲線(イメージ)】
![]()
一般的に10歳前後ぐらいまでに少しでも多くの言葉に触れ、その言葉が持つ概念を理解し、さまざまな世界観に触れる機会を積んでいることが、その後、前頭葉の発達に伴う人格形成や社会性、思考力の基盤となっていると言われています。
そのため、小学生のうちは、「読む・書く」を繰り返し練習することをおすすめします。特に「読む」経験を積むことで、文章への抵抗感が減り、自然と語彙力が伸びていきます。
小学中学年から増える「概念を表す言葉」が分かれ道
さらには、語彙にも2種類あります。
■語彙の種類
① 直接的な意味を示す語彙
- 単純なものの名前‥花、水、りんご など
- 身体防御として反射的に発する言葉‥熱っ、痛っ など
② 概念を表す語彙
小学中学年以上になるとこの②の概念を表す語彙が次第に増えてきます。この概念を表す語彙を理解できるかどうかが、国語が苦手になるかどうかの一つの分かれ目です。
なぜ、それが理解できないのか? それは多くの場合、その言葉が自身の経験として実感できていないからです。
たとえば、大好きなお友達が引っ越す当日。お見送りの最中に、胸に何かがこみ上げて来て、気がつけば涙がこぼれていた。お母さんが「さみしいね、悲しいよね」と言った。あ、そうか。これが「さみしい、悲しい」という気持なのか。子どもは、小さい頃からこうした生活体験を通じて、その瞬間の感情の一つひとつを「言語化」していきます。経験や体験に裏打ちされていない言葉は、自分の言葉として消化でできず、使いこなせないのです。
国語はすべての教科、そして社会生活の基盤
![]()
国語はすべての教科の基盤
少し理屈っぽい話が続きましたが、もうお気づきの方もいらっしゃると思います。国語はすべての教科の基盤なのです。
小学校では、すべての教科で「基礎知識」を蓄えることに主眼が置かれています。中学・高校、大学へとつながる「基礎の基礎」を身につける。解答テクニックを要するような問題処理能力を養うよりも、先々の知識の山をより高く積み上げるために、広くしっかりとした裾野を築くことを目的としています。そのために「新しい知識に触れて理解し、興味を覚え、学ぶことの喜びを知る」ことこそが、小学生にとっては何より重要です。
先生の話がわからないから授業がつまらない
小学校のうちは、社会をはじめ理科もほぼ記憶教科です。そこに必要なのは、先生の話を聞いて、あるいは教科書を読んできちんと理解し、面白いと感じられること。
算数も然りです。4年生ごろ算数を苦手にする子どもが増えてきますが、そのつまずきの原因の一つが、その頃に増え始める「文章題」です。計算云々の前に、問いの文章が読めていない、何を問われているのかがわからないのです。
授業で先生が話していることがよくわからない。教科書に書かれていることを正確に読み解けない。そんな気持ちで授業を受けるとしたら――お子さんにとって授業は、面白いどころか、つらい時間になってしまうかもしれません。
さらに言えば、国語は社会生活の基盤
さらに言えば、国語はこれから歩んでいく社会生活の基盤です。
たとえば、電化製品などの取扱説明書は、小学校6年生が読んで理解できるレベルで書かれています。また、新聞や契約書は、高校3年生が読んで理解できるレベルです。
つまり、社会で自立して暮らしていくためには、こうした基本的な国語力が欠かせないのです。
小学低学年で身につけたい国語学習の習慣
![]()
語彙を増やしたいなら漢字を覚える
【漢字の成り立ちから知識を増やす】
![]()
「言葉の森の旅」に出る喜びを知る
これらの漢字の成り立ちや関連知識は、辞書には多かれ少なかれ載っています。また、「もの知り」と言われる人や「雑学」に長けた人には、子どもの頃、辞書が好きだった人が少なくありません。
こうした「辞書好き」の人は、よく「言葉の森の旅」に出かけます。たとえば、「愛」という言葉を辞書でひくと、こんなふうに記されています。
1.かわいがる。いとしく思う。いつくしむ。いたわる
愛妻・愛情・寵愛(ちょうあい)・親愛・溺愛(できあい)・母性愛
2.男女が思いあう。親しみの心でよりかかる。
恋愛・求愛
当然ここでまた、「よく知らない言葉」に出会います。「いつくしむ」と「いたわる」はどう違うのだろう?「寵愛」とは、「恋愛」とは何だろう?「恋」と「愛」は何が違うのだろう?
「愛」を調べ始めたのに、興味のままに「いつくしむ」や「恋」という言葉も調べはじめ、それぞれの意味や違いにも気づいていく。これが、辞書を愛読書とする人が「もの知り」や「雑学に長けた人」になる理由です。
映画やドラマにもなった三浦しおんさんの小説「舟を編む」には、まさにそうした「言葉の森の旅」に出ることの楽しさや喜びが描かれています。まだ見たり読まれたりしたことがないお父さんやお母さんは、一度その奥深い旅の魅力を感じてみてください。
「紙の辞書」を使う習慣づくりを
先述の通り、小学校中学年以上では「概念を示す語彙」が増えてきますが、こうした「言葉の森の旅」を楽しむ習慣ができていれば、「実際の経験や体験を伴わない言葉」であっても「自分なりにイメージした世界観」は作っていけるのです。
そのためにお勧めするのが、「紙の辞書」です。スマホの辞書では、その言葉の意味が複数画面に分かれていたりすると、最初に表示された意味しか目に留まりません。さらには、「恋」と「愛」のそれぞれのページを行きつ戻りつしながら、見比べることも難しいからです。
どんな力をつけるべきか?その具体策
![]()
「ステップアップ講座」の国語のプリント学習の特長
ここからは、さらに具体的に「どんな力をどうやって身につけるべきか?」という具体的な勉強法をご紹介します。例として、アクシスのステップアップ講座が行っている学習法に基づいて説明します。
ステップアップ講座は、いわゆる「プリント学習型」のコースです。特長は2つあります。
特長① 無学年制
学年に合わせるのではなく、一人ひとりの子どもの学力に合わせて学習を進めていく
特長② スモールステップ
細かいステップで積み上げられている教材
授業では各教科1~2枚のプリントを解き、ご家庭で実施する宿題を持ち帰ります。小学校相当では全部で600枚のプリントが用意されていますが、無学年制ですから、たとえば小学5年生の子どもがJ6(小6相当)のプリントに取り組むこともあります。
【ステップアップ講座の国語教材の全体構成】
![]()
基本となる「4つの力」を並行・反復して学習
ステップアップ講座の国語のプリントは、どのレベルであっても次の「4つの力」を意識して作られています。
■小・中学校で鍛えるべき4つの力
① 語句
文字を正しく読み書きする
②文の構造
文の構造(例:主語⇔述語の関係、品詞の違いや働きなど)を理解する
③文の表現
表現上のルール(副詞の呼応<例:全然…ない など>
段落の展開<例:たしかに…だが など>)を覚える・理解する
④文の理解
①②③を駆使しながら、文章の内容を正確に読み取る
これらを水平的に鍛えながら、螺旋階段を上るようなイメージで次第に国語力を向上させていきます。
【ステップアップ講座の国語教材の全体構造】
![]()
■小学生・中学生相当教材(J1~J9)
文章の内容を正確に読み取る「理解」の領域を主要な学習分野とし、
その最終目標を「読解(要約)」において構成されている。
■高校生相当教材(J10以降)
読解(要約)を中心に学習する。
ステップアップ講座では、この4つの力こそが、小・中学校の時に重点的に鍛えるべき「国語力」だと考えています。
意外とできていない文法の理解
また、教室現場で感じる「国語学習の盲点」は、文法力の弱さです。
■文法の学習内容例
○主語・述語とは?
- その関係(例:○○は△△した、主語・述語のねじれ など)
○品詞の違いやその働き
- 名詞/代名詞/指示代名詞の違い など
- 形容詞と副詞の違いと働き(例:副詞は動詞を修飾する など)
- 助詞/助動詞の違いと働き(例:てにをは、助動詞の活用 など)
これらは、文章をより正確に理解できる「便利なルール」です。一度しっかり体系立てて学び、適切に理解すれば、それこそ一生使える知識だけに、小学生のうちからしっかり身につけておくべきです。
また、小学校のうちにこの「文法」という概念とその操り方を習得しておけば、中学に入ってからの「英語学習」にもよい影響を与えます。
[関連サービス]
アクシスのプリント学習「ステップアップ講座(算国英)」
親が家庭でできること
![]()
音読させると、いまの国語力がわかる
ご家庭でできることで、もっとも重視すべきは「音読」、文章を声に出して読ませることです。とりわけ小学校低~中学年時には、この「音読の習慣づくり」が大切です。
Q1. 次の文章を、音読してください。
→わたしは、あめのひには、あめをたべたくなります。
→私は、雨の日には、飴を食べたくなります。
小学低学年のひらがなが多い文章では、かえって難しく感じるかもしれません。音読させれば、雨と飴の違いをイメージでき、読み分けられているのかどうかがすぐにわかります。
Q2. 次の二つの文章を音読し、違いを述べてください。
(1)みさきちゃんは、「放課後は河川敷で一人で遊んでいる」といつも言っています。
(2)「みさきちゃんは、放課後はいつも河川敷で一人で遊んでいる」と言っています。
この2文では、言っている「人」と「時」が異なる可能性があることにお気づきですか?
(1)みさきちゃんは、「放課後は河川敷で一人で遊んでいる」といつも言っています。
→ 言っているのは「みさきちゃん」本人で、「いつもそう言って」いるようです。
(2)「みさきちゃんは、放課後はいつも河川敷で一人で遊んでいる」と言っています。
→ 「みさきちゃんはいつも河川敷で遊んで」いるらしく、そう言っているのは「みさきちゃん以外の人」のようです。
Q1.は語彙力があるかどうか。
Q2.は主語・述語の関係や品詞の違いや役割、それらから成る文意・文脈を正しく把握できているかどうか。
言葉一つひとつをどう発音するか、文章のどこをどう区切って読むか。さらにいえば、「放課後(ほうかご)」や「河川敷(かせんじき)」という漢字を読めていないかもしれません。読めていないならば、その意味を正確に理解できているかも疑わしいのです。
つまり、子どもは今どの程度の「読む力=国語力」を持っているのか、おおよその見当がつきます。そして間違っている箇所があれば、そこを問い直したり、具体的に教えてあげたりするきっかけにもなるのです。
日常的な会話や体験・経験の大切さ
教室運営の現場でたくさんの親子のあり方を見てきました。なかには、およそ学年にはふさわしくないほど、豊かなコミュニケーション力を持つ子どももいます。そうした子どもに共通して言えるのは、「普段の生活の中で親子がたっぷりと会話している」ということです。
これは、何も国語の問題に関する会話が必要なわけではありません。夕ごはんを食べるときに、今日学校であった話を聞き質問する。それで十分です。自分が感じたことを自分の言葉でアウトプットする。聞かれたことについて考えて、話をまとめて声に出す。そうした「コミュニケーションの量」が多いほど、言語力(国語力)は鍛えられていきます。
同様に、先述の通り、語彙力を高めるためには豊かな体験や経験も大切です。子どもが好きな趣味や興味、たとえば昆虫が好きなら、たまには近くの公園で昆虫採集に付き合ってみてはいかがでしょう。
「好き」や「夢中」は、子どもが自分から調べ、知識を増やしていける原動力です。そこに、体験や経験という“燃料”を足してあげれば、自ずと自分で学び、考える力は高まります。ぜひ、そうした刺激の与え方も意識してみてください。
レベルに合わない本を無理やり読ませない
「書店や図書館で子どもが選ぶ本が、学年から考えるととても幼い内容で、物語や小説を読まそうと思っても全然読んでくれない。」というご相談をいただくことがあります。それは、本人が「読まない」のではなく「読めない」というケースが多いと感じています。その本を読もうとしても、漢字が読めない、語句の意味がわからない…となるとおそらく冒頭の2~3行で読むことが苦しくて諦めてしまうのです。
そうなると「本(文章)を読むこと」=「しんどいこと」となり、ますます読書に苦手意識を持ってしまいます。
そうならない為にも、まずは子どもが興味を示す本をなんでもいいので読ませてあげてください。場合によっては漫画でも大丈夫です。自分に合ったレベルの本を読み、その内容を理解し面白いと感じれば、読書そのものへの興味も自然と湧いてくるはずです。
中には「キングダム」をきっかけに三国志に詳しくなり、同時に人並み以上に漢字に詳しくなった生徒もいました。
まずは子どもが本に興味を持てるように、保護者の方も焦らず温かく見守ってサポートしてあげてください。
まとめ
![]()
最後に、こうして「親がすべきこと・してはいけないこと」をお伝えすると、中には「本当にできているだろうか…」と自分を責めてしまう保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかしその必要はありません。こうしたコラムに目を通したり耳を傾けてくださる方は、お子さまのために「どうしたらいいか」を考え、意識を変えようとしている方だと思うからです。
子どもたちが学力を積み上げていく時にまず必要なものは「環境」です。ここでいう環境は塾や習い事による学習環境ではなく、子どもたちの生活環境を指します。
子どもたちの世界は非常に狭く、大きくは学校と家の二つに分けられます。特に家庭は子どもの心の安定に大きな役割を果たしています。愛情を感じられること、栄養のある食事をとれること、清潔な服を着られること。こうした安心できる環境があるからこそ、子どもたちは学習に取り組むことができるのです。
ですので、あまり堅苦しく考えず、これまで通り愛情を持ってお子さまに接しながら、私たちのアドバイスも時々思い出して取り入れてみてください。
それでも悩むことがあれば、ぜひ一度、個別指導Axisにお越しください。学習相談だけでももちろん大丈夫です。日々の学習や進路のアドバイスなど、お一人おひとりに親身に寄り添い、サポートさせて頂きます。