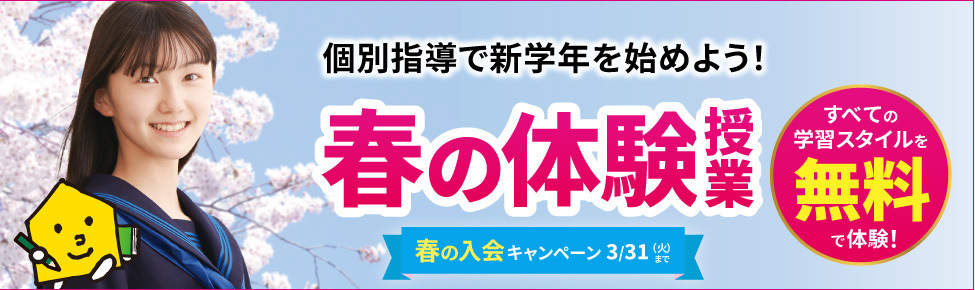小学校高学年が冬休みに意識してほしいこと
冬休みは次の学年への準備期間
年が明ければすぐに次の学年が待っています。特に高学年では中学に直結する大切な内容を学習するので、それらが身についていないと中学からが本当にたいへんになります。
たとえば、算数では割合や速さ、比、図形など、より深い思考力を必要とする単元を習います。国語は記述や文法の学習が本格的になり、抽象的な語彙も増えてきます。苦手や不安を次の学年に持ち越さないためにも、冬休みで解決する必要があるのです。
また、冬休みの宿題は年内に終わらせるのが理想です。そうすることで、後半は理解の浅い単元の復習にじっくり取り組むことができます。
[関連ページ]算数が苦手にならないための勉強法!苦手が生まれる理由や親ができることを解説
[関連ページ]国語力を伸ばすためには?家庭でできることや勉強法を解説
ゲームや動画はルールを決めて
冬休みは2週間といえども、不規則な生活をしているとなかなか元に戻れなくなってしまいます。正しい生活習慣をつけるのは時間がかかるのに、崩れるのはあっという間。休みだからといって好きなだけゲームをする生活はNGです。
家庭内で話し合って必ずルールを決めましょう。ここで油断するとそのままズルズルと中学生になり、そのときにはルールを決めようとしても子どもからの反発が出てうまくいかないことが多いものです。
小学生のうちに自律の第一歩を踏み出せるよう環境を整えましょう。ルールは親が一方的に「こうしなさい」と言うのではなく、子どもが納得して守れるものにするのがポイントです。