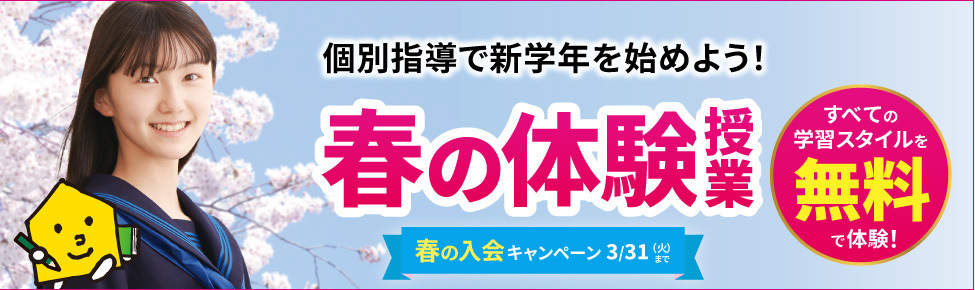「算数嫌い」はなぜ起こる?
「好き」と「嫌い」が両極化しやすい算数
小学生にとっての算数を知るうえで興味深いデータがあります。小学生(全学年)に「一番好きな教科」を聞いたところ、1位は算数(22.5%)でした<※2位/体育(17.5%)、3位/図画工作(14.0%)>。
同時に「一番嫌いな教科」も聞いてみると、実はこちらも算数が1位(24.3%)になっています。<※2位/国語(19.3%)、3位/体育(7.1%)>
どうやら、小学生にとっては、算数は「好き・嫌いがはっきりと分かれる教科」のようです。
小学校の算数は、「学年ごとに積み上げていく」教科
「好き」になってくれれば問題ないのですが、一方で「嫌い」になられては困ります。ではなぜ「嫌い」なってしまうのでしょう?
おそらくそれは、算数を習っていく途中のどこかでつまずき、そこから先の問題が解けなくなってしまったからです。
算数は「学年ごとに習う知識を積み上げながら」学びます。小学校の算数ではおもに、
- 数と計算
- 量と計算 ( 時刻、長さ・重さ・面積・体積・速さなど )
- 図形 ( 三角形、四角形、円、球、台形、多角形、線対称・点対称など )
- 数量関係 ( 表、棒・円・帯グラフ、百分率、比例・反比例など )
の分野を学びますが、なかでも重要な「数と計算」を例に見てみると、各学年では次のような内容を順を追って学び、学年が上がることに難しくなっていきます。
【 数と計算 各学年で学ぶ内容(一部) 】
| 1年生 | 加法・減法 など |
|---|---|
| 2年生 | 乗法、九九、簡単な分数 など |
| 3年生 | 除法、小数 など |
| 4年生 | 小数の加減乗除 など |
| 5年生 | 異分母分数の加減、 分数と小数の乗除 など |
| 6年生 | 分数の乗除、 分数・小数の混合計算 など |
基本的には、それまで習ったことがきちんと理解できていなければ、次には進めません。さらには、併行して学ぶほかの分野(量と測定/図形/数量関係の知識)も重ねて理解していくことが必要なため、どこかでつまずくと「わからないこと」が分野をまたいで一気に増えてしまうのです。
子どもを苦しめるカリキュラムオーバーロード問題
もう一つ、子どもの学習環境で課題とされているのが「カリキュラムオーバーロード」です。カリキュラムオーバーロードとは、学校の授業が質・量ともに過剰になることで、子どもや教員に大きな負担がかかっている状態をいいます。
たとえば算数の教科書一つをとっても、「ゆとり教育・ゆとり世代」といまを比較すると、ページ数は約1.8倍に、授業時間内にこなさないといけないページ数も1.2ページから1.8ページに増えています。
また、平日1日の平均授業時間数は低学年で5.2時間、高学年にいたっては6時間。つまり、多くの内容を毎日5〜6時間授業で学んでいるという状態であり、小学生の負担感は大きくなっているのです。
そうした環境で、もしどこかでつまずいてしまったら…。「どんどん進まざるをえない授業」だけに、ますます「置いてけぼり」にされてしまいます。
いま小学生の子どもをもつお父さん・お母さんは、まさに「ゆとり教育・ゆとり世代」の方が多いと思います。自分の小学校時代の記憶のままに子どもに勉強の話をしても、学習環境や負担感はまったく変わっています。そのことは常に意識しておいてください。
【内容が過多になった教科書(『東京書籍 算数小学5年』のページ数と標準時間数)】
| 対応する 学習指導 要領 |
教科書の ページ数 |
標準 時間 |
標準時数 あたり ページ数 |
|---|---|---|---|
| 1989年 学習指導 要領 |
212 | 175 | 1.2 |
| 1998年 学習指導 要領 |
174 | 150 | 1.2 |
| 2017年 学習指導 要領 |
310 | 175 | 1.8 |
※ゆとり教育・ゆとり世代とは?
ゆとり教育:1970年代後半の「詰め込み教育」に対する反省のもと、1990年代後半~2000年代初頭にかけて実施された教育方針。
ゆとり世代:一般的に、1987年4月2日から2004年4月1日に生まれた、義務教育期間中に「ゆとり教育」を受けた世代を指す。2025年時点で21~38歳に相当)
宿題が少なくなっていることも苦手になる原因?
近頃、「自分たちが小学生の頃よりも、宿題が少なくて心配」というご相談を、保護者の方からいただく機会が増えています。この「宿題が少なくなっている」ことは、算数にとってなおさら「喜ばしいこと」とは言えません。なぜなら「宿題が減る≒演習量が減ってしまう」からです。算数において、数的感覚や計算力を向上させるためには、演習が欠かせません。これも「算数が嫌い(苦手)」という子どもを生み出す原因の一つになっているかもしれません。
小学生のうちに鍛えておくべきは計算力
先ほど、小学校の算数では4つの分野を学ぶというお話をしましたが、なかでも小学生のうちに鍛えておいた方がよいのは「数と計算」です。これは小学校の算数の基本で、さらには中学・高校の数学の基本。化学や物理などの理系教科にも欠かせないものです。
より早く正確に計算するには、「数に対する感覚・センス」を身につけることが大切です。ここでいう「感覚・センス」とは、「才能」などではなく、「カラダが覚えている条件反射的な刷りこみ」のようなものです。
例)
「8」と「7」という2つの数字を見た瞬間に、「5」や「9」という数字もあわせてイメージできますか?
☞ 8+7=15(繰り上がりの理解につながる)
☞ 17-8=9(繰り下がりの理解につながる)
もちろん、最初のうちは、指を折って数えながら計算してもかまいません。しかし、多くの問題をこなし、何度も何度も繰り返し計算していれば、いちいち指を折らずとも関連する数字がパッと頭に思い浮んでくるようになります。
「九九」は、お経を唱えるように諳んじる
計算力の土台となるのは「九九」で、加減乗除のすべての基礎です。
余談ですが、「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」の「羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶(ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそうぎゃてい ぼじそわか)」といったお経文を諳んじている小学生がいます。きっと「鬼滅の刃」に影響されたんですね。おそらくその深い意味までは知らないでしょう。それでも反射的に口をついてすらすらと読み上げることができる。「九九」は、それぐらい自分のカラダと一体化するまで覚えましょう。
ちなみに、IT/AI先進国・インドは数学大国です。その秘訣は、小学生で習う「インド式計算」にあると言われています。2桁の掛け算までなら暗算で解ける(覚えている)のです。日本の「九九」は「たかが1桁」ですから、覚える気になればあっという間です。
こうして、小学3年生ごろまでの低学年のうちにトレーニングを重ね、「数に対する感覚・センス」を身につけ、すそ野の広い計算力の基礎を築いておくことが大切です。