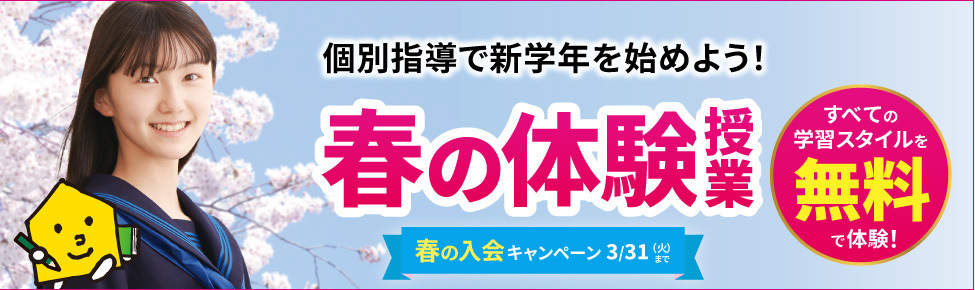オンライン学習とは?
さまざまなサービスや商品がいっぱい。
通う時間もいらず、通信環境とパソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末があれば、時間と場所を選ばずに、いつでもどこでも勉強できるスグレもの、それがオンライン学習です。昨今は、新型コロナウイルス感染症の流行により、このオンライン学習に分類されるツールやサービスが充実しています。
しかし、ひと口に「オンライン学習」と言っても、サービスや商品はさまざま。YouTubeなどで配信される、映像授業がいつでも視聴できる「オンデマンド授業」や、スマホアプリでドリル問題を解くもの、通信講座を受講、学習管理ができる「e-ラーニング」形式のもの、さらには対面授業と同じ授業を、Zoomなどでオンライン受講できる「オンライン授業」など…。まずは、これらの違いを知ることが初めの一歩です。
教える人とつながるか?双方向性があるか?
初めに着目すべきは、「双方向性の有無」です。つまり、教える人とつながって質問や会話ができるか? 双方向性がないものは「リアルタイムのオンライン学習」ではなく、「Webを使った学習教材」と言った方がより正確です。