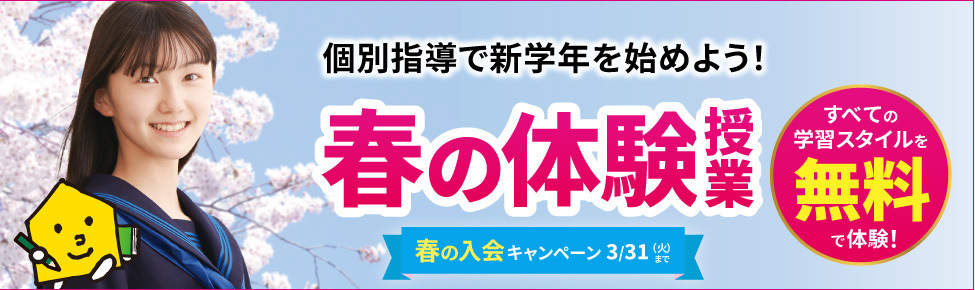学力検査では、中学校で習ったことをどれだけ理解しているかが試されます。最近は、知識だけでなく「思考力・判断力・表現力」が重視され、「資料の読み取り」や「自分の考えや結果に至った理由を述べる」といった、覚えた知識を活用する問題が多くなっています。こうした入試問題の出題傾向を知っておくことで、受験勉強で必要な対策がわかります。
英語
2026年度/令和8年度
出題傾向
A問題は文法問題1つ・読解問題2つ、B問題は読解問題2つから構成されています。C問題は大問6つで構成されています。 A・Bの読解問題ではスピーチや対話文が中心になり、Cの読解問題では、短めの英文が多く出題されます。英作文では、Aは5語程度、Bでは20語程度、Cは文字数の制限はなく、比較的長い英文を書くことになります。リスニングは、A・B問題では応答文やイラストや表を選択する問題が出題され、C問題は設問や指示がすべて英語で放送されるほかに、放送内容の要約を英語で書く問題が出題されています。
対策のポイント
長文読解は速く正確に!
長文読解の配点が全体の半分以上を占め、Aでは約400語以上、Bでは約600語の英文を読むことになります。過去問や対策問題を繰り返し解き、正確に速く解けるようにしましょう。また、C問題の英作文では自分自身の努力や成功の体験についての出題が多いのでそういった作文の練習をしてくと良いでしょう。
リスニングは日頃から!
リスニングでは5W1Hの疑問詞や、教科書で習った会話表現が重要です(C問題では、英問英答の形式です)。教科書や問題集、過去問の音声を利用し、会話文や発表形式の英文をスクリプトを見ながら「聴く」ことから慣れていきましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスニング | 正しい答えを選ぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 絵や地図を使う | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メモ・グラフ・表を完成する | − | − | − | − | |
| 日本語[英語]で答える | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自分の考えを英語で書く | − | − | − | − | |
| 発音・アクセント | 発音・アクセント | − | − | − | − |
| くぎり・強勢・抑揚 | − | − | − | − | |
| 読解 | 英文和訳(記述) | − | − | − | − |
| 脱文挿入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | − | − | − | − | |
| 要旨把握 | − | − | − | − | |
| 語句解釈 | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | − | − | − | − | |
| 段落・文整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指示語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 会話文 | − | − | − | − | |
| 文法・英作文 | 和文英訳 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 単語の穴埋め | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 正誤問題 | − | − | − | − | |
| 言い換え・書き換え | − | − | − | − | |
| 英問英答 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 条件英作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自由英作文 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4/4/8 | 4/4/8 | 4/4/8 | 4/3/6 |
| 小問数 | 34/30/34 | 34/29/34 | 34/29/34 | 26/21/26 |
| リスニング | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 英作文 | 4/4/1 | 4/4/1 | 4/4/1 | 4/4/1 |
数学
2026年度/令和8年度
出題傾向
A・B問題は大問4つの構成で、「小問集合・中問集合・一次関数・(平面)図形(三平方の定理を含む)」です。C問題は大問3つの構成で、「小問集合・平面図形・空間図形(三平方の定理を含む)」です。 A・B問題の大問1・2では「正・負の数、文字と式、多項式、平方根、確率、関数(グラフ)」などから、C問題の大問1では「多項式、平方根、確立、関数、二次方程式」などから出題されています。C問題の大問1の関数(グラフ)、大問2の図形、大問3の空間図形では、思考力が問われる、かなり複雑な問題が出題されています。
対策のポイント
A・B問題では、大問3・4にかける時間を確保する!
A・B問題では、前半の小問集合と中問集合を速く正確に解き、後半の関数や図形の問題に時間をかけることが大切です。 広い範囲を繰り返し練習し、学校で習った各単元の基本的な解法、公式をしっかりと頭に入れておく必要があります。後半の図形の問題は、学校の定期テストに比べて難易度が高いです。各図形の特徴を押さえ、問題演習を多くこなしましょう。
C問題では、解ける問題に時間を割く!
C問題は全体をもれなく解こうとすると、数学が得意な人でも時間がなくなります。小問集合では、ケアレスミスを無くし、早く正確に問題を解く力が必要です。また、関数や図形問題は、設問の文量も多く、内容も複雑であるため、学校の問題集など、通常の教材では対応できません。過去問や対策問題に繰り返し取り組み、解ける問題に時間を割けるように練習しましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数と式 | 正負の数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 文字式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 方程式・不等式 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 式の計算 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 連立方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平方根 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 多項式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2次方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 | 比例と反比例 | ◯ | − | ◯ | ◯ |
| 1次関数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 y = ax2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 図形 | 平面図形 | ◯ | − | − | ◯ |
| 空間図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平面図形と平行線の性質 | − | − | − | − | |
| 図形の合同 | − | − | − | − | |
| 図形の相似 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 円周角と中心角 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 三平方の定理 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| データの活用 | データの分布・比較 | − | − | ◯ | − |
| 確率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 標本調査 | − | − | − | ◯ |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4/4/3 | 4/4/3 | 4/4/3 | 4/4/3 | |
| 小問数 | 24/23/18 | 24/23/17 | 27/24/17 | 24/24/17 | |
| 記述問題 | 図形の証明(説明) | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 |
| その他の説明・証明など | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 立式・解法の過程の記述 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | |
| 作図(図形) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 作図(グラフ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国語
2026年度/令和8年度
出題傾向
構成は大問5つで、漢字が1つ・随筆や論説などの文章読解が2つ・古文が1つ・作文が1つです。 A・B・C問題に共通して、漢字の問題や、大意や説明を中心とした記述問題が毎年頻出されています。漢字の問題は多く出題されていますが、基本的に「読み」の問題は中学生までに習う漢字、「書き」の問題は小学生の間に習う漢字です。作文問題は必ず出題されており、A問題では180字以内、B問題では260字以内、C問題では300字以内で、B問題とC問題はアンケートの回答結果を基に自分の考えを理由付きで述べる形式です。
対策のポイント
大意・説明の記述問題に慣れる!
記述問題が多く出題されますが、筆者の考えをまとめる練習が必要です。文章中に出てくる言葉を用いてまとめる力をつけましょう。特にC問題はA・B問題に比べて難度が高く、記述問題の配点が高いです。指示語や接続語に注意し、速く正確に読む訓練を積みましょう。
C問題は特に!日頃から時間を意識した訓練を!
まずは受験の際に自分が挑戦するのはA・B・C問題のいずれになるのかを把握しておきましょう。問題の種類によって、作文の字数が変わってきます。短い試験時間の中で、読解問題3つと併せて字数の多い作文を完成させる力が必要ですので、日頃から“書くスピードを速く!”“読むスピードも速く!”を意識しましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢字・語句 | 漢字(読み・書き・筆順・画数・部首) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 熟語(三字熟語・四字熟語) | − | − | ◯ | − | |
| 語句(ことわざ・慣用句) | ◯ | − | − | ◯ | |
| 文法 | 文と文節 | − | − | − | − |
| 品詞・用法 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 敬語、その他 | − | − | − | ◯ | |
| 表現・情報 | グラフ・図表の読み取り | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 話し合い | ◯ | − | − | − | |
| 伝え方の工夫 | − | − | − | − | |
| 課題作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聞き取り問題 | − | − | − | − | |
| 文学史 | 文学史 | − | − | − | − |
| 現代文(読解) | 主題・表題 | − | − | − | − |
| 大意・要旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 情景・心情 | − | − | − | − | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文脈把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文章構成 | − | − | − | − | |
| 指示語 | − | − | − | − | |
| 接続語 | ◯ | − | − | − | |
| 脱文・脱語補充 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 古典 | 古文のかなづかい・古語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 古文の会話・主語 | − | − | − | − | |
| 古文の展開 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 文章のジャンル | 論説文・説明文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 記録文・報告文 | − | − | − | − | |
| 小説・伝記 | − | − | − | − | |
| 随筆・紀行・日記 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 詩 | − | − | − | − | |
| 和歌(短歌) | − | − | − | − | |
| 俳句・川柳 | ◯ | − | − | − | |
| 古文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | ◯ | ◯ | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 23/23/21 | 25/23/20 | 25/22/19 | 24/23/20 |
| 記号解答 | 9/7/6 | 6/7/6 | 9/8/9 | 7/5/7 |
| 記述式解答(漢字の読み書きも含む) | 14/16/15 | 19/16/14 | 16/14/10 | 17/18/13 |
理科
2026年度/令和8年度
出題傾向
小問集合のない大問4つで構成されており、それぞれ物理・化学・生物・地学の4分野に分かれています。 どの分野・単元からもまんべんなく出題されますので、苦手な範囲を作らないようにする必要があります。生徒の実験・会話文形式の問題が出題されており、問題文も長くなっています。推測だけで解ける問題がある一方で、知識の実践的な活用が必要な問題もあります。全体的な問題の難易度はそこまで高くはありませんが、高得点獲得には十分な読解力が必要となります。
対策のポイント
大問(分野)ごとに出やすい問題が決まっている!
物理分野の問題では「電気」や「物体の運動」、化学分野の問題では「化学変化と質量」や「水溶液」、生物分野の問題では「遺伝」、そして地学分野の問題では「天体の問題全般」が多く出題される傾向にあります。用語や公式などを見直しておきましょう。
問題量をこなす時間管理が大事!
出題される問題の数は多いですが、難易度はそこまで高くありません。飛ばさず丁寧に問題文をきちんと読み、実験結果から流れを考察できるよう、基礎的な用語や手順をおさえておきましょう。時間内に速く解けるよう、演習を重ねておきましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 力のはたらき | ◯ | − | − | − |
| 光と音 | − | ◯ | − | − | |
| 電流 | − | − | − | ◯ | |
| 電流と磁界 | − | − | − | − | |
| 力のつり合いと合成、分解 | − | − | ◯ | − | |
| 運動の規則性 | ◯ | − | − | − | |
| 仕事とエネルギー | − | − | ◯ | − | |
| 化学 | 物質のすがた | − | − | − | − |
| 水溶液 | − | − | − | ||
| 状態変化 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 物質の成り立ち、原子・分子 | − | − | − | ||
| 物質の化学変化 | − | − | − | − | |
| 化学変化と物質の質量 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 水溶液とイオン、電池とイオン | − | − | ◯ | ◯ | |
| 化学変化と電池 | − | − | ◯ | − | |
| 生物 | 生物の観察と分類の仕方 | − | ◯ | ◯ | |
| 生物の体の共通点と相違点 | − | − | − | − | |
| 生物と細胞 | − | − | − | ◯ | |
| 植物の体のつくりと働き | − | ◯ | − | ◯ | |
| 動物の体のつくりと働き | − | − | ◯ | − | |
| 生物の成長とふえ方 | − | − | − | ◯ | |
| 遺伝の規則性と遺伝子 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 生物の種類の多様性と進化 | ◯ | − | − | ◯ | |
| 地学 | 身近な地形や地層、岩石の観察 | − | − | ◯ | − |
| 地層の重なりと過去の様子 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 火山と地震 | − | − | − | − | |
| 自然の恵みと火山災害・地震災害 | − | − | − | − | |
| 気象観測 | − | − | − | − | |
| 天気の変化 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 日本の気象 | − | − | − | − | |
| 自然の恵みと気象災害 | − | − | − | − | |
| 天体の動きと地球の自転・公転 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 太陽系と恒星 | ◯ | − | − | ||
| 分野融合 | エネルギーと物質(物理・化学) | − | − | − | − |
| 自然環境の保全と科学技術の利用(化学・生物) | − | − | − | − | |
| 生物と環境(生物・地学) | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 小問数 | 36 | 36 | 34 | 33 |
| 記号解答 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 短文記述 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 計算問題 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 図・グラフ、モデル | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 語句記述 |
社会
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問4問構成になっており、小問数は約38~40問に及びます。地理・歴史・公民の分野をまたいだ融合問題も出題されています。出題形式は選択問題が中心ですが、資料の読み取り問題や記述問題もあるため、時間のペース配分が重要になってきます。日頃から時間を計って演習し、選択問題・記述問題それぞれにかける時間の感覚をつかんでおきましょう。また、語句の漢字指定がある問題も多いため、正確に書く練習をしておかないといけません。ケアレスミスには要注意です。
対策のポイント
資料を読み取る力をつける!
地理や公民では、グラフや表から情報を読み取る問題が必ず出題されます。過去問や対策問題をたくさん解いて、出題形式に慣れていきましょう。また、歴史では教科書に掲載されている絵巻物などの史料が出題されます。いつの時代の、どんな出来事なのかがきちんと説明できるように意識して学習していきましょう。
歴史は流れをしっかり理解しよう!
歴史分野からの出題が地理・公民と比べると高くなっています。広い時代にわたって出題されるのも特徴です。「一問一答」形式の演習で語句を暗記していくことと合わせて、教科書をしっかり読み、時代の流れをおさえておくことで、年代の並べかえ問題にも対応できるようになります。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 分野 | 出題内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理的分野 | 日本の姿 世界の姿 |
地形 | ◯ | ◯ | − | ◯ |
| 気候 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 人口 | − | ◯ | − | − | ||
| 産業・貿易 | 第一次産業(農林水産業) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 第二次産業(工業) | ◯ | ◯ | − | ◯ | ||
| 第三次産業(商業・サービス業) | − | − | − | ◯ | ||
| 貿易 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 地域 | アジア州 | ◯ | − | − | ◯ | |
| ヨーロッパ州 | − | − | ◯ | ◯ | ||
| アフリカ州 | − | − | − | − | ||
| 南北アメリカ州 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| オセアニア州 | − | ◯ | − | − | ||
| 九州地方、中国・四国地方 | − | − | ◯ | − | ||
| 近畿地方、中部地方 | ◯ | − | − | − | ||
| 関東地方、東北地方、北海道地方 | − | − | ◯ | − | ||
| 歴史的分野 | 日本史 | 平安時代まで | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 鎌倉・室町時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 戦国・江戸時代 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ||
| 明治時代以降 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 世界史 | 古代 | − | − | − | ◯ | |
| 中世 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 近世 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 近・現代 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| テーマ史 | 政治・外交史 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 社会・経済史 | − | − | − | ◯ | ||
| 文化史 | − | ◯ | − | − | ||
| 公民的分野 | 政治 | 現代社会と私たちの生活 | − | ◯ | − | − |
| 個人の尊重と日本国憲法 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 現代の民主政治、三権分立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 地方自治 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 経済 | 消費生活と流通 | − | − | ◯ | − | |
| 企業と生産活動 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ||
| 財政、国民生活と福祉 | − | ◯ | ◯ | − | ||
| 国際 | 地球社会と私たち | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 経済と貿易 | − | − | − | ◯ | ||
| 環境問題 | − | − | − | ◯ | ||
| 時事問題 | − | ◯ | − | − | ||
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 出題形式 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 小問数 | 40 | 38 | 38 | 40 |
| 記号解答 | 23 | 24 | 26 | 25 |
| 用語記述 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| 文章記述 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 作業・作図 | 0 | 0 | 0 | 0 |