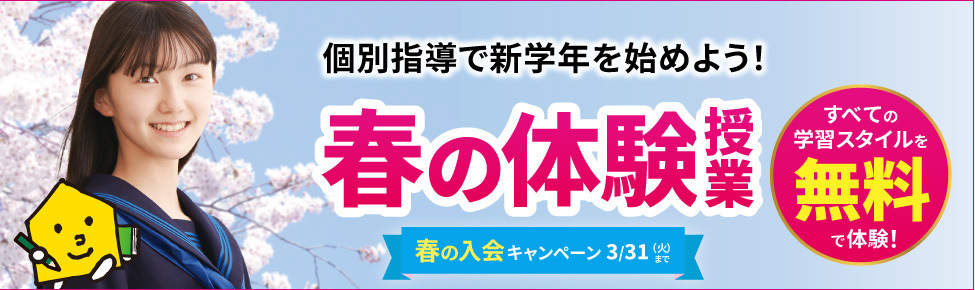正式教科になった小学英語 何を学ぶ?
3・4年生で「外国語活動」、5・6年生は成績評価する「教科」に
2020年度の学習指導要領の改訂により、小・中・高の英語教育のあり方が大幅に変わりました。なかでも大きく変更されたのが小学校で習う英語です。小学校3・4年生で「外国語活動」が始まり、5・6年生では正式な「教科」として成績評価の対象となりました
まずは、その小学校の英語学習の概要を見てみましょう。
【小学校の年間標準授業時数】
<単位:時間>
(参考: グローバル化に対応した英語教育改革実施計画)
3・4年生は「聞く・話す」
小学校3・4年生では、「外国語活動」として、標準時数で年間35回(週1回程度)の活動が行われます。
到達目標は、「聞くこと」「話すこと」を通じて外国語でのコミュニケーション能力の基礎を身につけること。簡単に言えば、「英語に慣れる、親しむ、会話する」です。
5・6年生は、3・4年生の英語にプラス「読む・書く」
小学校5・6年生では、正式な教科「外国語」として、標準時数で年間70回(週2回程度)の授業が行われます。
到達目標は、3・4年までの「聞くこと」「話すこと」に加えて、「読むこと」「書くこと」を学び、より深くコミュニケーションを図るための基礎力を育成することです。
正式な教科になったので成績評価も行われ、通知表にも記載されます。
【求められる英語スキル:3年生~4年生】
・挨拶や感謝、身の回りのことに関する質問など、簡単な語句や表現を聞き取り、話せる
・事前に準備をして、人前で自分の考えや気持ちなどを話せる
<3年生>
「Hello!」「How are you?」「How many?」「What do you like?」など
<4年生>
「What time is it?」「Do you have a pen?」「What do you want?」など
【求められる英語スキル:5年生~6年生】
- ・英語で短い話を聞き、概要を理解できる
- ・英語の質問を聞き、その場で考えて答えられる
- ・話す内容を整理し、英語で自分の考えや気持ちなどを伝えられる
- ・文字と音の関係を理解する
- ・語順を意識しながら書き写せる
<5年生>
「How do you spell it?」「What do you have on Monday?」など
<6年生>
「My Summer Vacation」「What sport do you want to watch?」など
2.小学校の英語学習の現状と課題
公立校では担任の先生が教えるケースが多い
基本的に小学校では、担任の先生がすべての教科の授業を行います。そのため英語の授業も、3・4年生/5・6年生いずれも、ALT(Assistant Language Teacher<外国語指導助手>)や英語専科教員が行うケースは少なく、3・4年生で6割程度、5・6年生で5割程度は担任の先生が授業を担当しています。
これも小学校の英語学習の抱える課題の一つに挙げられています。
大学の教職課程で「小学生への英語の教え方」を学んでいない先生はたくさんいます。また、正式教科になってからまだ日も浅いため、英語を専門としない担任の先生でも英語専科教員レベルで教えることができる「標準的英語学習モデル」は、まだ確立されてはいません。
小学英語を教える先生や学習プログラムの質をどう向上させていくのか?これらは学校の現場が真剣に取り組まなければならない大きな課題です。
自治体でも「温度差」の大きい英語教育への取り組み
また、ALTの配置数などの英語教育への取り組み方にも、自治体によって大きな差が生まれているようです。
「英語を聞く・話す」機会を多く持たせるために、ネイティブスピーカーや専科教員を積極的に配置したり、成績評価の指標づくりに取り組んだり、英検などの外部検定の活用などが検討されている自治体がある一方で、地方の自治体、とりわけ人口規模の小さい市町村レベルでは、財源や人材面での制約も多いため、対応できる施策は限られてしまいがちです。このように、英語教育に大きな温度差があることも小学英語の課題となっています。
「中1ギャップ」が生まれやすい教科・英語
「中1ギャップ」という言葉をご存知ですか?学級担任制が教科担任制に変わることや、授業内容や成績のつけ方の変化など、生活や学習環境に馴染めず様々な不調を抱えることを言います。
そんな中、今新たに「英語の中1ギャップ」という言葉をよく耳にするようになりました。「英語」という教科の中で、「中1ギャップ」が生まれやすいとされる理由は次の通りです。
中学で英語が嫌いになる原因「小学校700語問題」
2020年度の学習指導要領の改訂では、小学校で扱う英単語数は600〜700語程度と定められました。これは単語の「書き取り」までを求めているものではなく、子どももスペルを覚えるまでに習熟しているとは限りません。
中学校で学ぶ単語数は1600〜1800語程度です。こちらは前回の学習指導要領の改訂によって、1200語から約600語も増えています。そして、この1600〜1800語には小学校で扱う600〜700語は含まれていません。
【2020年度学習指導要領改訂に伴う
必要単語数の変化】
2020年度より前は英語に慣れ・親しむだけで良かったものが、現在は小学5・6年生の間に約700語の英単語を「ローマ字読みではなく正しく読めて、スペルも書ける(読み・書き)レベル」まで習熟していることを前提にして始まるのです。
その結果、「単語のスペルまでは習熟していない」子どもが中学で学ぶ語数は、最大で700語+1800語=2500語にのぼり、いきなり大量の新しい単語に出くわす事態が起きます。 これがいわゆる「小学校700語問題」で、英語に苦手意識を持つ原因の一つです。
覚えなければならない量に対して、授業時間が足りない
このように、小学英語は「従来なら中学校1年生で習う英語」を小学校に前倒しして学習するように設計されています。2024年度には教科書改訂も行われましたが、とある小学英語の教科書では、それまで697だった語数が825にまで増えました。こうした傾向は今後も続くと思われます。
そうでありながらも、標準時数は5・6年生でも年間70回(週2回程度)と限られています。覚えなければならないことは多いのに、その割には授業時間数が足りていないのです。
お父さん・お母さんの「危機意識」も大切
「小学校で英語を習う」という経験がないお父さん・お母さん世代は、小学英語に対する意識がどうしても低くなってしまいがちです。
もちろん、皆さん「これからの時代、英語は大切ですよね」ぐらいの認識はお持ちです。しかし、ご自身が英語を学び始めたのは中学生からです。自然と「いまの成績はちょっとくらい悪くても、中学からしっかり頑張れば大丈夫」と思ってしまいます。
自分の時代の経験や常識にとらわれることなく、小学生のうちから「英語も国語や算数と同じく、大切な教科の一つ」と理解して、その成績についても気にかけてあげることがポイントです。
できない子どもとできる子どもが2分化
実際に、中学1年生の英語の成績分布をみると、できる子どもとできない子どもの差がはっきりしています。
ほかの教科の場合、できない子ども・できる子どもは、「富士山のシルエット」のように、平均値を中央にしてほぼ左右均等に出現します。しかし英語は、小学英語の習熟の差が中学1年生で顕著に現れ、「ふたこぶラクダ」のように、できない子どもとできる子どもが2分化しているのです。
中学英語の教科書の作り方にも大きな変化が!
中学校の教科書の考え方も、昔と違って「コミュニケーション(会話すること)」を重視する方向に変わっています。
お父さん・お母さん世代には、「Reading」「Grammar(文法)」は、きっと馴染みの深い言葉ですよね? これまでの教え方は、文法は文法としてしっかりと別に時間を割いて学習する構成になっていました。
きっと、以下のような「単元名」を覚えている方も少なくないと思います。
- ・be動詞(This is a pen.)と疑問文(Is this a pen?)
- ・一般動詞と助動詞(can,will,may,mustなど)
- ・命令文(動詞を文頭に)
- ・人称代名詞(I,you,he,she,it,we,theyなど)と主格―所有格-目的格(I-my-meなど)
- ・疑問詞・疑問文(what,when,where,who,how)
- ・現在進行形(be+~ing)
こうした英語の基礎となる文法知識一つひとつを水平的に積み上げ学んでいくのが、これまでの「文法学習」のスタイルでした。
しかしいまの教科書は、会話文を軸として構成され、その会話に関連する文法知識を散りばめるような作りになっているため、体系的に理解できず、文法が身に付きにくいのが現状です。しかし、英語学習を効果的に進める上で、文法は欠かせない存在であるため、授業をスムーズに理解できるよう、基礎となる文法力を養うことが大切です。
小学英語、どうやって勉強すればいい?
中学校で英語が苦手になる原因は、努力不足だけではない
先述のように、小学校では英語は好きだったのに、中学に入ってからは一気に苦手科目になってしまったという子どもは少なくありません。
実際に、中学生になってから英語を習いにくる子どもの多くは、単語力や文法知識などの基礎的な力が不足しています。しかしこれは、子どもの不勉強だけが原因とは言い切れません。
小学校の「楽しい英語」から、突然に「文法を意識した英語」へ
小学校では「楽しい英語」を中心に学んできたのに、中学校に入ったら、突然大量に単語や文法や構文の知識をテストで問われるようになった。しかも小学校で習った単語は、すでにしっかり覚えていることが前提になっている。なんだかいきなり「文法を意識した英語」に様変わりしてしまった。子どもにしてみれば、そう感じてしまっても無理はありません。
このように、「聞く・話す」がメインだった英語の授業が「読み・書き」メインになったことや、単語テスト・定期テストが始まったことなどのギャップが、英語を苦手にさせてしまう大きな原因です。
小学校のうちに、いっぱい英語に触れて、楽しく話して、興味を持つ。そうした「英語との接点」を増やすこと自体は、とても良いことです。せっかくのその貴重な経験をムダにしないためにも、小学英語と中・高英語を効率よくつなぐ「体系的な学び」が必要です。
無学年制・スモールステップの「ステップアップ講座」
それでは、ここからはもう一段深掘りして、「小学英語は何をどう勉強すればよいのか?」という具体的な勉強法についてお話します。例として、アクシスの「ステップアップ講座」が行っている学習法に基づいて説明します。
「ステップアップ講座」は、いわゆる「プリント学習型の講座」です。
<ステップアップ講座の特長>
- ①学年に合わせるのではなく、一人ひとりの学力に合わせて学習を進める無学年制
- ②細かいステップで積み上げられているスモールステップ方式
<ステップアップ講座の英語教材がめざすこと>
- ①意識的に基本構文を身につけ、英語の構造を理解させる
- ②英文に慣れ親しませる
- ③未知の単語や熟語を調べる力を育てる
- ④音声リズムで英語感覚を磨く
文法などの「英語の構造」を体系的に理解・習熟することを重視
英語の文法を学ぶには小学校4年生相当の国語力がある事が望ましいことから、「ステップアップ講座」の英語は小学校4年生から受講することができます。プリント5枚で1つのテーマを学習します。
基礎となるアルファベットの学習から始まり、小学校6年生相当のプリントからは文法の学習に進みます。プリントは、下のような4つの領域に区分されています。
【プリント1枚の構成】
この4つの領域を見ていただくと、「ステップアップ講座」は文法を体系的に理解・習熟することに重きを置いていることがお分かりいただけると思います。
この5枚1テーマを20セット(=100枚のプリント)やり終えれば、1学年相当が終了します。もちろん、間違えたりわからないところがある場合には反復学習し、きちんと理解してから次のセットに進みます。そのため「わからないままの積み残し」が無く、自信を持って次に進むことができます。
第二言語を効率よく学びたいなら、文法を鍛える
では、なぜ「ステップアップ講座」では文法などの体系的な理解を大切にしているのか? その理由を説明します。
いまこれを読んでいらっしゃるほとんどの方は、日本語を母国語とし、英語は「母国語以外の言語(第二言語)」だと思います。
よくテレビCMなどで、「英会話をマスターするなら、ネイティブスピーカーに習った方がよい」といったフレーズを耳にしますが、これは半分ホントで、半分は間違っています。
言語教育学的にいえば、この指導法は「direct method(直接教授法)」と呼ばれるものです。たしかに英「会話」に限れば、ネイティブスピーカーを相手に恥ずかしがることもなく、きれいな発音を聞きながら学んだ方がよいこともたくさんあります。
しかし、これはいわば「赤ちゃんが成長とともに母国語を自然と習得していく」ような学び方で、毎日膨大な量の英語を浴びることができる環境と時間が必要です。日本に住んでいて、そんな条件で学べる中学生や高校生はほぼいないでしょう。
それならどうするか?日本語を母国語とする人が英語(第二言語)を学ぶ際には、語彙、文法や構文などを覚えてその使い方を習熟するほうが、相乗的に理解も進んで成果を得やすいとされています。
大学受験や各種英語検定で問われるのも「文法」的な力
大学受験の問題で、実際に出題されるのは長文とリスニングがほとんどですが、その読解力とリスニング力を支えるのが確かな文法知識です。また、海外留学で求められるTOEFL®TESTや、ビジネス現場で活用されているTOEIC®TESTなども、会話力もさることながら、まずは語学の土台となる文法的な力が測定されます。
小学英語は好きだったけど、中学に入って苦手になった…。そういう子どものほとんどは、この文法的な力がついていません。逆に言えば、そこを基礎からしっかり鍛えさえすれば、英語の試験は飛躍的に得点できるようになります。
英検を上手に活用する方法や注意点は?
英検は学習指導要領を踏まえているため、子どもが学年相応の英語力を身につけているかどうかを測りやすいというメリットがあります。
中学卒業程度の力が身についている目安になるのは3級合格です。とするならば、小学生のうちにめざしたいのは5級です。そこまで行ければ、学年相応の力がついていると判断してもよいと思います。
もちろん、小学校の授業を差し置いて、英検だけを一生懸命勉強することに意味はありません。英検は、学習成果を「見える化」する目標であり、モチベーションとして活用してください。
またこうした検定は、どうしてもその合否ばかりが気になり、不合格なら何度でも挑戦したくなりますが、本当に上手な検定の使い方は「弱点分析」です。受かったにしても落ちたにしても、そればかりに目を奪われるのではなく、試験問題を振り返って弱点を補強する勉強法を組み立てるようにしてください。
とはいえ、英語は「ただの言葉」。積み上げれば必ずできる!
「中1ギャップ」を浴びて英語を苦手にしてしまうと、そこから先、英語は理系にも文系にも必須の科目だけに、大学受験までずっと苦労してしまいます。小学英語と中・高英語を効率よくつないで得意科目にできるよう、小学生のうちから「体系的な学び」で基礎を固めることを検討してみてください。
一方で、「もうすでに中学に入って苦手になってしまった」というケースでも、悲観することはありません。英語は、数学や物理のようなひらめきやセンスが必要な教科ではなく、言い換えれば「ただの言葉」に過ぎません。
中学1年生ならまだまだ時間はありますし、たとえ3年生だったとしても「やる!」と覚悟を決めれば、挽回のチャンスはあります。少なくともテストの成績だけに限っていえば、「覚えれば必ず成績は伸びる」のです。
そうしてたくさん覚えていくうちに、自然と言葉のルールや文の構造などの規則性に気づくようになり、それによってさらに理解が深まり、「もっと楽しく学ぶ」ことができるようになります。その延長線上で、将来、英語を活かした仕事に就くことも不可能ではありません。
英語は成果が見えにくく、英語力の向上を実感しづらいですが、単語・文法を積み上げれば必ずできるようになります。一つひとつをていねいにじっくりと頑張りましょう。
個別指導アクシスは、現状の学習のお悩みや、その先のゴールをしっかりと見極めて、お子さまに合った学習プランをご提案しています。ぜひ、お近くの校舎へお問い合わせください。
\ アクシスは、全国500校超 /
お近くの校舎へお気軽にお越しください。
この記事を書いた人
個別指導Axis教育本部
学習プランナー
権藤 理恵(ごんどう みちえ)
能開センター・個別指導Axis
教育本部 英語プロジェクト
坂井 豊美(さかい とみ)
この記事を見た人へのオススメ記事
-
個別指導Axisの校責任者の役割とは?
-
中学受験は必要か?わが子に最良の選択は何か迷うときの考え方【新小学5年生・6年生】
-
小学生の冬休みの過ごし方!各学年の勉強のポイントをご紹介
-
算数が苦手にならないための勉強法!苦手が生まれる理由や親ができることを解説
-
【小学生】国語力を伸ばすためには?家庭でできることや勉強法を解説
-
塾の選び方のポイントを解説。失敗しないために事前にやっておくべきこととは?
-
【春休みの勉強法】周りと差がつく、やるべきこと3選。春期講習の必要性についても解説!
-
個別指導塾の料金は?料金の内訳と塾の選び方、確認すべきこと
-
オンライン学習ってどうなの?メリットや通塾との違いを解説!
-
子どもが宿題をやらない理由は?宿題を習慣化するポイントや注意点
-
算数と数学の違いとは?特徴や学習の目的、苦手意識をなくすポイント
-
中学受験に向いている子の特徴|基礎知識やメリット・デメリット
-
小学生のうちに学習習慣を身につけるために、親が意識すべきこと
-
中学受験しない子が、小学生のうちに上位高校・大学進学に向けて準備するべきこと
-
アクシスに入塾した決め手とは? 会員生・保護者さまへの入塾アンケート
-
保護者の皆さまからの口コミ・評判お客さまアンケート
-
アクシスってどんな塾?アクシスの教室でインタビュー
-
なぜ、プログラミング教育は必修に?