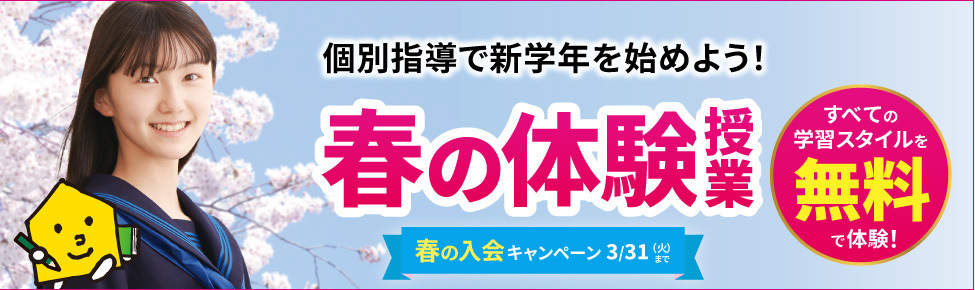大学受験対策
志望校合格に向けた勉強法とは
高校生は忙しい。限りある時間の中で効率よく勉強してきた先輩たちの勉強法を受験勉強に取り入れよう。
反復学習で習慣化
-
山口大学 経済学部 合格
T.Kさん - 期間を決め、期日までに単元ごとなどのきりがいいところまで終わらせる。その期間が終わればまた新しく期間と内容を設定して取り組む。これを繰り返すことで勉強の習慣ができ、記憶も定着されやすくなる。期間は1日や1週間など短い方が集中して取り組みやすくなる。期間が終わるごとに本当に理解、記憶できているか確認するために小テストなどを行うとよい。この勉強法は自分の苦手を把握しやすく、メリハリをもって勉強に取り組むことができる。 受験体験記を読む
スキマ時間を活用
-
福島大学 人間発達文化学類 合格
大関 楓良さん - スマホやタブレットに勉強アプリで勉強していました。問題集などを全て持つのは重くてかさばるからです。(利用していたのは理科・社会・古典・英単語などです)学校のタブレットに入っていた「classi」というアプリの学習トレーニングという機能も活用していました。朝の通学時や休み時間などのスキマ時間に行っていました。私自身集中力が長く続くタイプではないため、ゲーム感覚でできるタブレット型学習は合っていたと思います。 受験体験記を読む
友人と先生ごっこ
-
愛知教育大学 教育学部 合格
公原 ひよりさん - 放課後や休日に、学校へ行って友人と教室で「先生ごっこ」をして基礎的な内容を確認し合っていました。黒板も使うとより記憶に残ったように思います。友人が知っていて自分は覚えていなかったことが出てきたら、焦って覚えることができるし、ずっと机に向かって黙々と勉強するより楽しく復習ができました。この勉強法は、きちんと理解していないとよい先生になれので、勉強に熱が入ります。どの教科にも向いている勉強法だと思います。 受験体験記を読む
大学受験の
勉強スケジュール
コツコツ努力した先輩も短期決戦の先輩も、いつどうやって基礎を固めるか、それが合格へのカギだった。
基礎とアウトプット
-
九州大学 経済学部 合格
河﨑 真翔さん - 英単語は高校3年生になるまでには単語帳1冊をほぼ完璧にして、それからはそれが抜けないように通学の電車の中や学校の休み時間などの隙間時間を活用して勉強しました。数学は網羅系参考書を高校3年生の夏休みまでにひと通り解いて、基礎を固めるようにしました。また数学に関しては定期テストの勉強が意外と重要だと思っていて、そのときに単元ごとにしっかり復習をしておくことで受験期にいきてくることが多々ありました。日本史は参考書を読んでひと通りインプットした後に友達と一問一答をしたりとアウトプットすることをを重点的に勉強しました。 受験体験記を読む
基礎と演習の繰り返し
-
岡山県立大学 保健福祉学部 合格
田中 友菜さん - 私は最初、基礎の部分が頭に入ってなかったので、問題を解いても解けませんでした。なので、基礎を徹底的にさらい、定着させるために問題を解きました。そこで間違えたところを復習することでより定着させました。間違えて覚え直したことは、記憶に残りやすいです。このサイクルを毎日続けました。それと同時に、問題の解き方のコツなどをつかみながら演習を重ねました。するとぐんぐんと解けるようになっていきました。その中で少し発展的な問題も知識の組み合わせで解けたり、間違えても解説を読んで理解したりすると高得点を狙えると思います。 受験体験記を読む
本格的な受験勉強は
頻出英単語を極めることから!
-
宇都宮大学 地域デザイン科学部 合格
押久保 雪杜さん - 高校1.2年の英語の基礎力があまり身についていなかったので、本格的な大学受験に向けた勉強をする前の高校3年の夏休みに、遅れを取り返せるよう取り組みをしました。1つ目は、英単語を勉強する時に、しっかり覚えた単語と不安な単語の2つに分け、後者を単語帳ではない紙に書き、隙間時間に見るようにした事です。2つ目は、単語帳を使って覚えるときににしっかり定着させるために、睡眠前や起床直後に勉強したり、反復をするなかで、小テストのように定着しているかどうかの確認することで、基礎をしっかり積み上げていきました。 受験体験記を読む
大学受験の
科目別の勉強方法
やみくもに勉強しても成績は上がらない。回り道をしないよう、先輩たちの取り組み方を参考にしよう。
英語力を向上させるには
-
慶應義塾大学 法学部 合格
宮崎 想良さん - 大切なことは単語→文法→解釈→長文の手順である。長文は文・単語の集合であるため、読解力・速読力が効率的に上昇する。また、文法の勉強は、英文を正確かつ短時間で理解するために、文型、句、節の分け方の理解が最も重要である。上記に加え、さらに英語力の向上を図るのならば国語を勉強すべきだ。結局、英語を訳した後に現れるのは日本語の文であり、要約や文の構成を見抜くことが容易にできれば、必然的に英語の点数も向上するだろう。 受験体験記を読む
古文・漢文の勉強法
-
東京理科大学 経営学部 合格
山田 杏奈 さん - 高3の夏休みに個別で国語のコマを取り、基本的な用語や文法をはじめに固めた。特に、古文の助動詞では、意味や活用法などを暗記することで、その後の問題演習に役立った。また、漢文では句形や読み方を覚えることで、問題の得点を安定して稼ぐことができるようになった。基本的な部分が完成したら共通テストの形式の問題に多く取り組み、テストに慣れたり、古典単語の補充による文章読解の速度を上げることなどに取り組んだ。 受験体験記を読む
化学は言葉単体ではなく関連づけて覚える
-
広島大学 理学部 合格
S.Yさん - 高3の夏休みまで、教科書を使い、化学式や物質を式そのものや物質名として覚えていました。しかし、暗記量が多く、よくあやふやになっていました。そこで資料集を使った暗記に変え、化学式や物質を、見た目や反応の様子、グラフなどと関連付けて覚えることで、しっかり暗記できるようになりました。また有機化合物や高分子についても、物質が使われているものの具体例を覚えることで、性質や官能基から構造式につなげて覚えることができました。 受験体験記を読む
数学は自分の解法に根拠をもつ
-
埼玉大学 理学部 合格
柳田 健心さん - 問題を解くときに「問題文の雰囲気的にこの公式を使う」「今ここの単元の問題を解いているからこの公式だろう」という曖昧な勉強ではなく、「この値を求めるにはこの公式を使うのが効果的。なぜなら〇〇だから」という根拠をもてるように勉強する。これは数学の知識がない人に説明するとより効果的である。しかしどれだけ根拠を持とうと思っても問題によってはいつまでも理解できないときもあるので、その時は何時間も考えず、先生に教えてもらうと良い。 受験体験記を読む
世界史は
年表を作成して覚える
-
大阪教育大学 教育学部・昼間 合格
橋場 海聖さん - 出来事の年の暗記が苦手だったため、物事のつながりを見つけて年表を作っていました。一つひとつの出来事が重なり合い歴史が生まれることを意識すれば、一つの出来事を覚えるときに、背景となった過去の出来事も一緒に覚えることができます。そしてそれが影響して起こったことも見つけられれば、タテの繋がりはとても早く覚えることができます。ヨコの繋がりは、他国との交流で起こった出来事と関連付ければ2つの地域の事をセットで覚えることができます。 受験体験記を読む
共通テストは参考書完璧作戦!
-
京都教育大学 教育学部・昼間 合格
高橋 さくらさん - 私は、共テ1.2ヶ月前に完璧にする参考書を絞りました。時間の関係や効率的に、総合得点を伸ばすことを考え、5科目は参考書を1冊に絞り、何周もしました!他の教科は全く勉強しないわけではなく、問題集はやっていました。でもそれらは完璧を目指すのではなく、決めた5冊さえ完璧にしていれば大丈夫と思って取り組んでいました。すると自信がつくので、共テ当日もリラックスできました。全てを完璧ではなくどうしたら受かる確率が上がるのかを考えて! 受験体験記を読む
問題集・参考書の
活用方法
「反復は奇跡の勉強法」これはある先輩の言葉。地道な演習の繰り返しこそが志望校の問題を解く力になる。
最適な問題集で、
文系でも数学を強みに!
-
熊本大学 法学部 合格
奥園 梨穂さん - 数学が好きだったので得意科目にしていけば共通テストでも有利になると考えました。問題集の選定にあたっては塾の先生と相談しながら決めていきました。学校ではチャートを購入しますが、文系志望で2次試験では数学は出されないので、もう少しすっきりした基礎問題精講を自習用の問題集としました。分かりづらい解説についてはアクシスの授業時にしっかりと質問して解決しました。間違えた問題や解説を見てわかった問題に付箋を貼り夏休みまでに1周しました。2〜3周するうちに分からなかった問題の解法も理解して定着し、本番でも得点源になりました。 受験体験記を読む
決めた単語帳だけを
完璧にする気持ちで
-
関西外国語大学 英語国際学部 合格
江口 暁子さん - 時間がなかったので、1900語完璧にしようと思い、移動時間や他の勉強で疲れた時に単語帳を開き勉強しました。1回目で分からなかった単語、2回目で分からなかった単語と、マーカーで色分けして効率良く覚えました。なかなか覚えられない単語や過去問頻出単語も、付箋で色分けして探しやすいよう工夫し、直前までに4周はしました。過去問は3年分を3回しました。長文の分からなかった単語、和訳、なぜ間違ったかをしっかりと確認し、分からなかったところは塾で先生に聞きました。赤本に載っていなかい重要なポイントも教えてくださり、力になりました。 受験体験記を読む
物理の二次対策
-
山形大学 工学部 合格
谷高 陸斗さん - 二次試験で使う物理の記述問題の対策方法として、リードαを3周以上やっていました。やり方としては1周目はすべて解き、解けなかった問題には赤丸をつける。そして間違い直しで自分の納得のいくまで、理解しきったと思えるまで、答えを読み返して再び問題を解く。それでも分からない場合は、先生に聞く。2周目は赤丸のついているものだけをやる。2周目で間違えたものは青丸をつける。そして青丸をつけたものを次の日に3周目として解く。そうすることで、記述問題を解く力が自然と身につきました。 受験体験記を読む