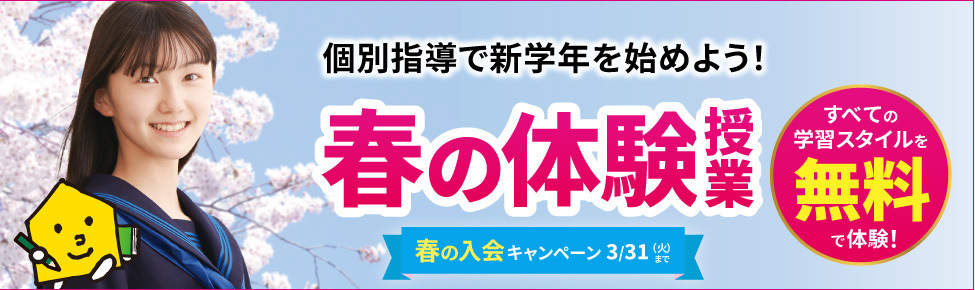大学受験の勉強はいつから始めたら良い?
![]()
大学受験の勉強開始時期は人それぞれですが、早く始めることにはメリットがあります。ただし、高校3年生からでも遅すぎるというわけではありません。自分に合ったタイミングを見つけましょう。
理想的なのは高校1年生から
できるだけ早いうちから志望大学を決め、受験を意識しながら勉強に取り組むことが理想的です。基礎力を身につけたり、学習習慣をつけたりしておくと、大学受験の対策を効率よく進められます。
特に、学校推薦を目指すなら、高3からではやや遅く、高1から定期テスト対策を重視して成績アップを図り、評定平均値を上げておく必要があります。
最も多いのは高校3年生から
受験勉強を始めるタイミングとして多いのは、高校3年生からです。
実際に、個別指導Axisの大学合格者アンケートによると、約6割の生徒が高3から本格的に受験勉強を始めています。
しかし、高2から始めたという生徒も約3割いることから、やはり早いスタートがアドバンテージになっています。とは言え、決して高3からのスタートが遅すぎるということではありません。
部活生であれば、高3の8月、さらに9月、10月から始めたというケースもあり、部活に打ち込んで培った体力・集中力と戦略で志望校合格を手にしています。
![]()
※個別指導Axis「2024年度大学受験合格者アンケート」より
受験勉強だけに集中できるようになる時期は人によって異なります。そのため、学校の授業や宿題、予習復習、テスト直しといった普段の勉強を大切にして、自分の実力や志望校のレベル、入試方式を踏まえ、計画的に取り組んでいきましょう。
大学受験勉強において、まずやるべきこと
![]()
大学受験勉強を始めるにあたって、まず行うべきステップがあります。これらを押さえることで、効率的に勉強を進められるはずです。
【Step1】志望大学・学部・学科を決める
志望大学、学部・学科が決まれば、勉強の方針が明確になります。最初は漠然としたイメージでも問題ありません。オープンキャンパスに参加したり、大学のホームページを見たりして、徐々に具体化していきましょう。
【Step2】現時点での学力を把握する
模擬試験(模試)などを活用し、自分の現状の学力を把握します。これにより、重点的に勉強すべき科目や単元がわかります。特に、大学入学共通テストや志望校の個別試験で配点の高い科目を中心に、自分の強みと弱みを確認しましょう。
【Step3】学習計画を立てる
志望校の入試日程を確認し、逆算して受験勉強のスケジュールを立てます。ただし、必ずしも計画通りには進まないこともあるため、スケジュールは柔軟に微調整していく必要があります。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を修正していきましょう。
【学年別】大学受験の勉強の進め方
![]()
大学受験の勉強は、学年によって注力すべきポイントが異なります。ここでは、高校1年生から3年生まで、各学年で取り組むべき内容を紹介します。
高校1年生
高校1年生では、学校の授業と定期テストを優先し、コツコツと基礎を固めることが何より重要です。学校で習った内容の復習をしながら、自分の得意・苦手な科目や単元を理解していきましょう。
苦手分野は、応用問題よりも基礎問題を繰り返し解いていくことがおすすめです。これにより、基礎を固め、自分の学習スタイルを確立することにつながります。
また、多くの高校では1年生の冬までに文理選択が行われます。大学の受験科目や就職・進学の選択などにも関わってくるので、後悔することがないように、しっかりと進路をイメージして文系・理系どちらで学ぶかを決めましょう。
高校1年生における大学受験勉強のポイントは、勉強習慣をつけることです。毎日の積み重ねが学力アップにつながります。大学受験勉強に必要な1日の勉強時間は一般的に学校授業を除いて、学年+2時間(高1→3時間)が目安です。
さらに、この時期から得意科目を伸ばしておくことも大事です。1科目でも超得意科目があれば勉強方法に自信がつき、何より心のゆとりが生まれます。
高校2年生
高校2年生では、苦手科目の克服に努めましょう。高校3年生ではやるべきことが多く、苦手を克服することに時間をかけられない可能性があるためです。
特に、英語・数学の勉強に注力することをおすすめします。これらの科目は習得するまでに時間がかかるためです。
また、この時期には具体的に志望校を検討し始めましょう。大学のホームページやパンフレットを見たり、オープンキャンパスに参加したりするのも良いでしょう。
高校2年生における大学受験勉強のポイントは、苦手科目を優先して勉強することです。苦手科目の点数アップは合格可能性を上げる一番の近道になります。
基本的な内容を復習し、教科書レベルを完成させて、入試レベルの参考書や問題集に取り組めるだけの力をつけなければなりません。定期テストや模試で「なぜ間違えたのか」を徹底的に分析して対策しましょう。
高校3年生
高校3年生では、志望校の合格最低点や配点、傾向を踏まえて、科目別に勉強計画を立てます。これにより、自分の課題を分析することができます。
夏までに基礎固めを終わらせ、秋からは応用力の養成や過去問題に取り組んでいきましょう。
秋からは志望大学や志望学部の問題形式を知り、過去問に慣れていくことが重要です。過去問や模試を活用して、短期間で得点力を伸ばす対策を行っていきます。
また、学校推薦型選抜や総合型選抜で受験するなら、小論文や面接対策にも注力する必要があります。
高校3年生における大学受験勉強のポイントは、「1学期」「夏休み」「2学期」「冬休み〜入試直前」それぞれの時期にやるべきことや到達すべきレベルを押さえて、計画的に学習することです。
また、模試の判定に一喜一憂しないことも大切です。A判定だから安心できる、E判定だから合格できないと、早々に結論を出すことはおすすめしません。
模試はあくまで途中経過です。判定結果が良くても悪くても、しっかり自分の弱点を分析し、日頃の学習に活かしていくことで志望校合格が近づきます。
[関連サービス]
「行きたい」大学、「学びたい」学部に行く|志望大学・学部別対策
塾・予備校に通うこともおすすめ
![]()
塾や予備校は大学受験対策に精通しているため、戦略的に受験勉強をしたい人に向いています。ここでは、塾・予備校に通うことをおすすめする理由を紹介します。
大学受験に関する情報を多く持っているため
塾や予備校は、大学入試の最新情報や傾向を常に把握しています。志望校の出題傾向や合格に必要な学力レベルなど、受験に直結する情報を得られます。
また、講師の指導実績や経験に基づいたアドバイスは、効率的な学習計画の立案に役立つはずです。
自習室などの環境が整っているため
多くの塾や予備校には自習室が完備されています。集中して勉強できる環境は、家庭学習ではなかなか得られない大きなメリットです。
また、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境は、モチベーション維持にも効果的です。スキマ時間を活用して効率的に学習を進められます。
適切なカリキュラムで勉強を進められるため
集団塾や予備校では、大学受験対策の講座レベルが科目ごとに複数設定されていたり、個別指導塾では、生徒一人ひとりに合わせてオーダーメイドカリキュラムが提供されたりします。
これにより、自分に必要な学習内容を効率よく学ぶことができます。また、定期的な模試や面談を通じて、進捗状況をチェックし、必要に応じて学習プランを調整することもできます。
こうした専門的なサポートは、特に勉強に不安を感じている受験生や保護者の方々にとって心強い味方となるでしょう。