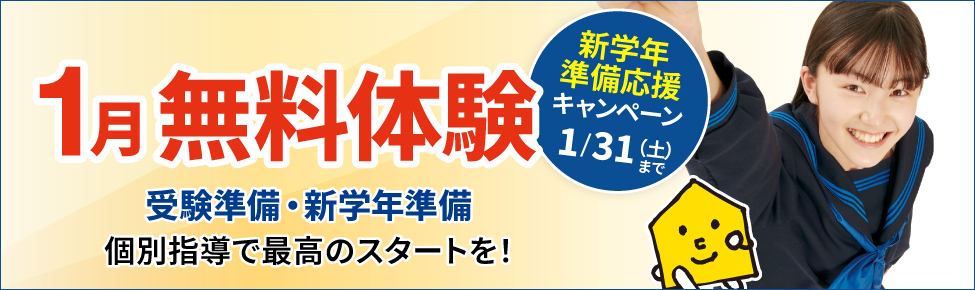いつまでに何を決めねばならない?
高1秋・高2秋・高3春に決めるべきこと
大学入試の受験対策を組み立てるうえでは、志望大学・学部は、可能な限り早くに決めた方が有利に働くことは間違いありません。
なかには中学生からすでに、医学部や看護学部、教育学部、建築学部などを受験すると決めている生徒もいます。しかしそれは、親の薦めであったり、親の仕事を見て憧れたり…といった「周りからの影響」を受けていることが多く、大半の生徒は、高校1年入学時ではほぼ「白紙」ですし、基本的にはそれでも問題はありません。
ただし、高1・高2・高3の各学年で、必ず決めてほしいことがあります。
【高1の秋まで】文理選択 高校によっては国公立か私立か?
多くの高校では、1年生の秋には、受験する大学を文系学部にするか、理系学部にするかを選ばねばなりません。あるいは、学校によっては「国公立コース」「私立文系コース」「私立理系コース」といった志望大学群で分ける場合もあります。
これは、受験時の試験科目を念頭に、2年次から必要な科目を効率よく学べるようにクラス編成するための選択です。
【高2の秋まで】科目選択 理系は数Ⅲ、文系は社会の科目選択がカギ
新たなクラスで2年が始まると、秋には受験を意識した科目の選択が求められます。ここでポイントとなるのが、理系は数Ⅲ、文系は社会(地・歴・公民)の選択です。
理系の大学受験では、基本的に理科の化学・物理・生物の中から2つを履修することが前提となります。さらにそのうえで数Ⅲの履修をするかしないのかは、決断のしどころです。
もちろん、数Ⅲが受験科目に課せられる学部・学科なら履修せざるを得ません。しかし、必須でない学部・学科なら数Ⅲは履修しないという選択もあります。数Ⅲは難度が高く、学習負担が大きいからです。受験生にとって学部・学科を選ぶ際の選択肢が増えるメリットはありますが、履修する際は慎重に考えましょう。
一方文系は、社会の科目選択がカギを握ります。「地理(地理探求)、歴史(日本史探求、世界史探求)、公民(倫理、政治・経済)」の中から、1~2科目を選ぶことになるので、志望大学で課される科目を意識して選びましょう。日本史と世界史の両方を選択する場合は、暗記量が爆発的に増えるため、慎重に考えましょう。
また、文系選択で国公立志望の方は、共通テストで「地理・歴史」「公民」から2科目を選択することになりますが、選択できない組み合わせもありますので、選択方法について注意が必要です。(例:公民の「公共、倫理」「公共、政治・経済」の組み合わせは不可など)
【高3の春まで】志望大学の偏差値帯にある「大学群」
3年生の春休みまでには、第1志望としたい「大学群」、たとえば「旧帝国大学」「地方国公立大学」「MARCH」「日東駒専」「関関同立」「産近甲龍」などを決めておくようにしましょう。
欲を言えば、「2年生の冬休み」までに決めることができれば、なお理想的です。多くの高校では、3年生で新たに習う科目を除けば、2年生2学期までに一通りの授業を終えるように時間割を工夫しています。となれば、そこまでに決めておけば、2年生の3学期は受験に必要な科目の1・2年次のおさらいと基礎固めに時間を充てることができるのです。
あえて「大学群」と言いましたが、「旧帝国大学」「地方国公立大学」「MARCH」「日東駒専」「関関同立」「産近甲龍」などの総合大学であれば、多少の違いはあれども似た学部があります。
またこの時点では、出願まではまだ8カ月程度、試験日までなら1年弱あります。当然、ここからの「伸びしろ」もあります。どこか一つに絞り込むというよりも、「この偏差値帯の大学」という広めの目標設定の方が、大学・学部選びの選択肢を狭め過ぎず、柔軟な受験対策を講じることもできます。