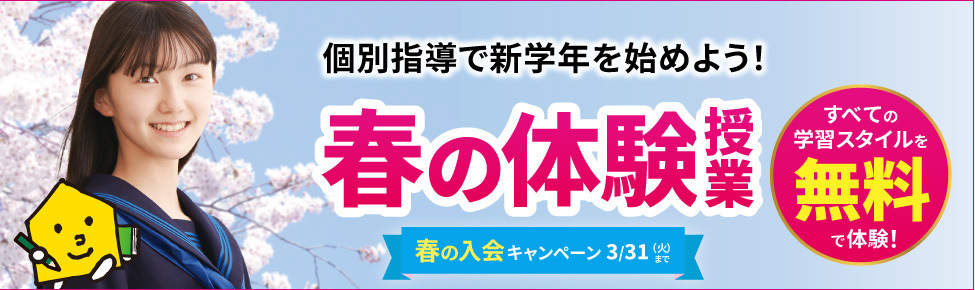志望理由書とは?
![]()
志望理由書は、学校推薦型選抜や総合型選抜で受験する際に提出が求められる出願書類で、その大学を選んだ理由や大学で学びたいことなどを述べ、入学したい意欲をアピールするものです。
近年、とりわけ私立大学では、学校推薦型選抜や総合型選抜による入学者が増えており、受験生の主体性や学ぶ意欲に対する評価がより重視されるようになっています。そのため、志望理由書の重要性は年々高まってきています。
[関連ページ]
大学推薦入試(学校推薦型選抜/総合型選抜)とは?複雑になった仕組みと種類・特徴を解説!
「学力に関する客観的評価」と並んで、「人物評価」に必要な書類
学校推薦型選抜や総合型選抜は、大別すると「人物評価」と「学力に関する客観的評価」の二つの視点から選考されます。
志望理由書は「人物評価」に必要な書類の一つで、出願時に提出が求められます。また、試験日に行われる面接や小論文も「人物評価」のための仕組みです。
一方の「学力に関する客観的評価」は、願書と同時に提出が求められる学校評定や学科試験などで評価されます。また、学科試験には、共通テストを利用する大学もあります。
【学校推薦型選抜や総合型選抜で求められる
書類や試験とその役割】
![]()
何が問われているのか?どう評価されるのか?
上図は、学校推薦型選抜や総合型選抜の受験に求められる書類や試験には何があり、それぞれがどんな役割を担っているのかを示しています。大学によっては小論文や学科試験が省かれる大学もあります。その場合には、志望理由書が合否判定に影響する割合はより高まることが予測されます。
志望理由書をどのように利用し、どの程度ウエイトづけしているかは、どの大学も公表してはいません。
あくまで想像の範囲にはなりますが、志望理由書は①入学意思を確認する、②一次審査の判断材料とする、③面接時の参考資料とするといった場面で利用されていると思われます。
また、選抜方式によって重視するポイントも異なっているようです。学校推薦型選抜では、第一志望(専願=合格したら入学を前提とする)かどうか。総合型選抜では、大学が求める学生像と自分の適性のマッチングを理解できているかなどが評価されていると考えてよいでしょう。
自己PRや小論文との違い
ところで、志望理由書と自己PR、小論文の違いを的確に答えられますか?いずれも「400字程度(多くても800字程度)の文章にまとめる」という書式は似てはいますが、似て非なるもの。それぞれで書かねばならない内容は異なります。
志望理由書は自分を志望大学に売り込む文書、つまり、自分は志望大学に入学するにふさわしい人物であることを説得する文書です。自分がその大学に入学すると大学にとってどんなメリットがあるのか?それが書かれていることが大切です。どれだけ魅力的な自己PRが書かれていても、大学側にメリットがないと判断されてしまうと評価は低くなります。
小論文は、アピールするためのものではなく、受験生の論理的思考力を測る、あるいは論述を通じて、どの程度の教養・素養を持っているか、どんな価値観や人生観を持っている人物なのかを測るために課せられるものです。
◾志望理由書・自己PR・小論文の違い
志望理由書<出願時に提出>
- 将来の夢や目標、大学で学びたい内容を書く
- 自分はその大学・学部にふさわしい人物であり、その大学で学ばねばならない必然性が高いこと書く
⇒志望する大学・学部はどんな特長を持っていて、
それが自分自身の目標にどう結びつくのか?そして、
それをやり遂げることができる資質を持っていることを書く
自己PR<出願時に提出>
- 自分を優秀な人間・価値の高い人間としてアピールするための書面
- これまでの成績や受賞歴、部活動などの学校生活での経験を述べ、
そこから得た教訓や成長をアピールする
⇒「私はこんなにすごい」という価値をアピールする
小論文<試験日に出題>
- 試験当日に出題された問題文(論文、解説文、評論文など)に基づき、それを要約したり、そこで述べられている意見について考察したり、自分なりの意見を論述する
[関連ページ]
小論文とは?構成や書き方のポイント、上達への対策【例文付き】
受かる志望理由書の書き方
![]()
志望理由書対策を練る際に、大前提として意識しておくべきことは、志望理由書は出願時に提出する書類だということです。そこが、試験当日に試験会場で限られた時間内で答えねばならない学科試験や小論文試験、想定外の質問にも即座に反応せねばならない面接試験などと大きく異なる点です。
出願時に出せるということは、「何度も書き直した完璧なもの≒推敲を重ねて多くの人の目のチェックを経て用意されたもの」を出してよいということ。きちんと準備する時間さえ確保できれば、説得力のある、よりよいもので勝負することができるのです。
2~3カ月程度の準備期間が必要
ただし、きちんと準備したいなら10回程度の推敲・書き直し、期間でいえば2~3カ月程度は必要になると考えてください。志望校への願書提出が10月末ごろなら、逆算すると、その前の学校への提出は概ね10月初旬ごろ。その2~3カ月前となると、夏休みが始まる時期には準備を始めるようにしましょう。オープンキャンパスへの参加も、準備のひとつとして効果的です。
評価を左右するのは「情熱・内容・表現」
志望理由書を書く際に気をつけておくべきポイントは、「情熱・内容・表現」です。
◾志望理由書で評価される3つのポイント
①情熱
- その大学で学びたいという強い思い。自分の学びや将来への意欲を示す。
②内容
- 大学にアピールできる「自分らしさ」。学んできたこと、得意なこと、経験してきたことを整理し、大学が求める人物像と重なる部分を示す。
③表現
- 思いを正しく、わかりやすく伝える力。せっかくの熱意や内容も、表現が曖昧だと相手に伝わらない。
この3つのポイントを意識しながらまとめるのは、簡単なようで意外と奥が深く、難しいものです。とりわけ「①情熱」を巧みに伝え、「②内容」の質を高めようとするなら、まずはきちんと「大学を知る」「自分を知る」ことが必要です。
大学を知ること自体は、大学のホームページやパンフレットなどの情報を丁寧に読み込んでいけば、比較的スムーズにできるでしょう。しかし、「自分を知る」作業は、これまであまり経験したことがないかもしれません。しっかりと時間をかけましょう。
◾️情熱を伝える・内容の質を高めるためにすべきこと
大学のことを知る
- どんな学風でどんな特徴を持った大学なのか
- どんな学び・研究をしているのか
- 学び方の特徴や教員は
- どんな力や人間が求められているのか
自分のことを知る
- 志望理由の深堀
- これまでの自分の経験の棚卸し
- どのような障害をどのように乗り越えたのか
- 志望校と自分の意思との合致度
- 入学にあたっての覚悟 など
自分を知ろう。過去・現在・未来の棚卸と言語化
先述した通り、志望理由書は自分を志望大学に売り込む文書です。自分は志望大学に入学するにふさわしい人物で、自分がその大学に入学すると大学にとってどんなメリットがあるのか、が書かれていることが大切です。
となればまずは、自分は何者なのか自己分析すること、そしてそれを上手に物語に仕立てることが大切です。
そのために必要なのが、自分の過去・現在・未来を棚卸して言語化するワークです。これにより、自身のビジョンや、高校生活などで培ったスキルや長所が明確になり、書くべき内容の要点が浮かび上がります。
以下、それぞれに必要な視点・切り口のサンプルを挙げておきます。これを参考にして、まずは一度、「自分とは何者なのか?」を考えてみてください。
過去
◾過去を書きだす視点
- 職業を決めるきっかけとなったできごと
- 強烈な記憶
- 好きな教科を決めるきっかけとなったできごと
- 文理選択を決定づけたできごと
- 校内での活動(クラブ・委員会・文化祭など)
- 好きだった先生
- 校外での活動(ボランティア活動・団体活動など)
- 人に負けない趣味
- 生老病死に関する経験
- 苦労した対人関係での経験
- 何かを成し遂げた経験
- 挫折の経験 など
■過去を語る具体的なエピソード(例)
部活動系
- ・小学校のころから野球を続けている
- ・高校最後の大会、ケガで背番号をもらえずに終わった
- ・初めての挫折
教科・学習系
- ・小学校のころから理科が好き
- ・工作の時間が楽しみだった
課外系
幼少系
- ・幼い頃は病弱だった
- ・小学校の時に体力をつけるために野球を始めた
プライベート系
- ・アルバム委員をやっており、細かい作業を頑張った
- ・テレビでプロ野球選手がスマートフォンを使ってデータ分析をしているのをみて、自分もやってみたいと思った など
現在
◾現在を書きだす視点
- 過去から得た価値観
- 現時点で人より勝っている能力
- 現時点で人より劣っている能力
- 志望校を選んだ基準
- 家族や友人の中で自分が果たしている役割
- 志望校や目標についての情報 など
■現在を語る具体的なエピソード(例)
事実系
- ・評定は3.7
- ・受験勉強を夏以降に始め、基礎の大切さを痛感している
価値観系
- ・結果を求めるのではなく、途中での努力や継続が重要だ
学習・学校系
- ・物理と数学が得意 英語が苦手
- ・情報やパソコンに興味がある
- ・部活やクラスではムードメーカー
- ・悩み相談を受けることが多い
職業系
- ・大好きな野球に職業として関わりたい
- ・スポーツ全般でも可
- ・野球が好きなのは、戦略が重要だから
環境系
未来
■未来を書きだす視点
- 特定の職業が決まっているなら「どのような○○」を想像
- その職業が果たす社会的役割
- 目標がないならどの方面か
- 世間に感じている違和感
- この世の中で改善したいこと
- 職業にこだわらない理想
- 尊敬する人物
- 30歳・50歳・70歳の自分
- 10年後・50年後の地球 など
■近未来(≒大学が求める生徒像)を語る具体的なエピソード(例)
学長メッセージ
- ・地域の発展と持続可能な社会
- ・自主、自律、共生の社会
学部紹介
- ・発展と融合
- ・社会との調和をめざすシステム工学
- ・地球との共生
学科紹介
- ・ロボットの制御技術や光工学、複合技術
- ・自動車、電機メーカーなど進路は多彩
アドミッションポリシー
- ・忍耐強い人
- ・好奇心旺盛、自主性、創造性
- ・論理的思考に強い
- ・分解や創作が好きな人
興味を持った研究室やワード
- ・システム制御・ロボティクス
- ・歩行ロボット
- ・目=カメラ=光学技術
- ・光による画像計測研究室
- ・センシング研究 など
■将来(≒10年後の自分)を語る具体的なエピソード(例)
将来の仕事
思いつくアイデア
- ・3Dのスコアボード
- ・道具にICを埋め込み、選手の調子を分析
- ・運動しやすい車いすやパワースーツ
- ・実物と同じ動きのピッチングロボット
将来挑戦したいこと
- ・新しい野球の魅力を伝えることで、野球人気を復活させたい
- ・何らかの事情で運動できない人たちに機会を提供したい など
表現を磨こう。書き始める段階で必要な作業
志望理由書を書く際に気をつけておくべき3つのポイント「情熱・内容・表現」のうち、仕上げる際のポイントが「表現」です。いよいよ志望理由書を書き始める段階で必要な作業は、大きく次のようになります。
■志望理由書を書く際に必要な作業
志望校に自分の何を伝えたいのかを整理
- 「自分を知る」作業を通じて言語化した「特筆すべき自分の魅力・特徴・資質」の中から、志望大学に伝えたいことを整理する
志望校の特長とフィットするようにブラッシュアップ
- 「大学を知る」作業を通じて整理した大学の特長と自分の相性がいかに適しているか、その物語をつくる
具体的なエピソードの選定
- 物語に必要なエピソードを選ぶ。エピソードのネタ自体は「普通によくある些細なネタ」でも構わないが、そのネタをどれだけ自分のオリジナルストーリーに仕上げられるか、どれだけ熱意が伝えられるか?がポイント
志望理由書を上手にまとめるための段落構成
- ①第一段落
志望を簡潔に示す
- ②第二段落
志望を決めたきっかけ・理由を書く
- ③第三段落
具体的なビジョン・社会的な意義・決意など
- ④第四段落
まとめる
志望理由書は、全体で400字程度(多くても800字程度)ですから、第一段落・第四段落は、不必要に文字数を取られ過ぎないよう、簡潔な一文でよいでしょう。
<第一段落例>
将来は○○○の仕事に就きたい、それが○○大学○○学部を志望する理由です。
<第四段落例>
以上の理由から、私は、貴学への入学を志望します。
大切なのは、第二・第三段落で、この二つで全体の90%程度を占める見当です。
第二段落では、なぜその学びに興味を持ったのかを自分の経験や気づきのエピソードに基づいて語り、さらにはそれをなぜこの大学で学びたいのかを自分なりのストーリーで語ることが大切です。
そのうえで第三段落では、そうしてこの大学で学んだ結果、どう社会に役立てていきたいのかを語ります。一貫性のある内容を記載することがコツです。
塾の上手な活用法
![]()
ここまで、テンプレートも紹介しながら、志望理由書の書き方をマニュアル的にアドバイスしてきました。しかし本来は、この種の文書に「書き方お作法」的なテンプレートやマニュアルは必要ありません。何よりも大切なのは内容、入学後に○○を学びたいという情熱が伝わるかどうか、それが本質です。
だからこそ、そこで再び「しかし」です。そんな大上段に構えた文書を、何のサンプルもなくいきなり書けるものでもありません。初めの一歩は、テンプレートをトレースしただけのものでもよいので、「まずは一度書いてみる」ことです。
「まず書いたこと」を起点にして、掘り起こし磨き上げる
実はそこから先こそが、塾の価値が試されるところです。
何かしらの思いや意志を示してくれれば、それをきっかけとして、会話することができます。会話できれば、生徒がどんな思いを持っているのかを掘り起こし、言語化することができます。そのコミュニケーション量が増えれば、文章を添削することもでき、磨き上げられます。
たとえば、「人の役に立ちたいから看護師になりたい」という一文が書かれていたとします。これを起点にして会話してみるなら…。
例)
先生: 人の役に立てる仕事なら介護福祉士もそうだよね、なぜ看護師になりたいの?
生徒: お年寄りだけでなく、いろんな年代の人のケガや病気を治す現場にいたいから
先生: じゃあ、医師の方がよくない?
生徒: 数学や理系科目がそこまでのレベルに達していないからかな?
先生: あれば医師をめざすの?
生徒: ひょっとしたら、ドラマで見た『チーム医療』に惹かれているのかも…
先生: チーム医療のどこに感動したの?
話の納得感や共感力など、先生との相性を確認して!
こうしたやり取りを重ねる中で、どんな文章の裏にも“その生徒だけのストーリー”が隠れていることがあります。それを引き出すのは、塾の先生の腕の見せどころ。
一人ひとりに合わせた指導や、その場に応じた柔軟なやり取りは、個別指導だからこそできることです。
だからこそ、まずは自分に合う先生かどうか、話してみて納得できるかを確かめることをおすすめします。