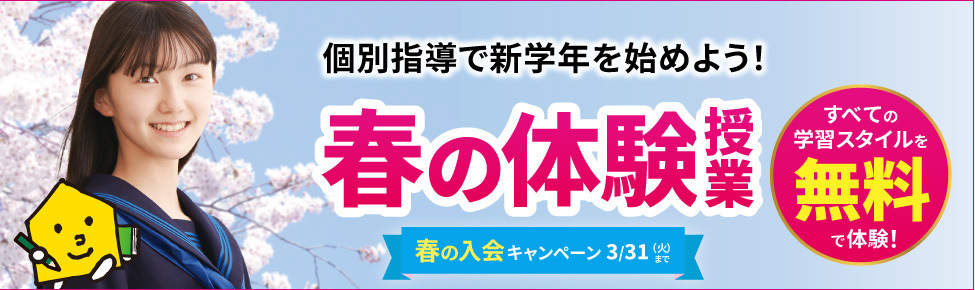勉強と部活動を両立するためにやってはいけないこと3選
![]()
限られた時間の中で勉強と部活動を両立するためには、規則正しい生活習慣と、子どもが安心できる家庭環境が必要不可欠です。基盤となる環境を整えるにあたり、まずは、時間がないからといって、やってはいけないことを押さえましょう。
(1) 時間がないからといって、睡眠時間を削るのはダメ!
まとまった睡眠時間を取る
睡眠不足だと、集中力が落ちて授業内容の理解が弱くなる、問題を解くパフォーマンスが落ちる、授業中に眠くなってやる気が起きない、免疫力が低下して体調不良を起こす、など、良いことはありません。
寝ている間に、浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」を繰り返しますが、その繰り返しが多いほど知識の定着度がアップすると言われています。まとまった睡眠時間を取ることが大切です。
眠いときは我慢せずに寝る
昼間に部活動の試合があったなど、疲れてどうしても早めに眠くなることがありますが、眠いのを我慢して勉強しても身につかないので、そういうときはさっさと寝てしまった方が良いのです。その分、翌朝少し早めに起きてやり残したことに取り組むなど調整して取り戻します。
毎日決まった時間に寝る
また、休みの前日は夜更かしをせず、毎日決まった時間にベッドに入り、朝も平日と同じ時間にきちんと起きるようにしましょう。
「休みだから朝は遅くまで寝ていてもいいか」という考え方のクセがついてしまうと、なかなか修正ができなくなります。起床、就寝時間を固定し、子どもに充分な睡眠をとらせることを常に意識しましょう。
(2) 時間がないからといって、家族や友だちとのコミュニケーションを減らすのはダメ!
家庭内での会話を大切にする
親も子どもも忙しいと、家庭内での会話が減ってしまいがち。意識してコミュニケーションを取ることが重要です。
そのとき、つい「勉強は?」と言ってしまいそうになりますが、親は子どもが「勉強をしているかどうか」だけを気にするのではなく、「何を勉強しているのか、何ができるようになっているのか」にも関心を向けましょう。
子どもの勉強に関心を持つ
親が勉強に参加するのも良いと思います。といっても、理科や社会の重要語句の問題を親が出して、子どもが答える…というようなことだけではありません。
たとえば、食卓に、四字熟語やことわざなどが載っているカレンダーを置いて話題にしたり、テレビのニュースを見て意見を言い合ったり、今どんなことを習っているの、と聞いたりするだけでも構わないのです。
要は、親が子どもの学習内容に関心を持ち、目標を応援する空気を家庭内に作ることです。子どもには「勉強しなさい」と言って、親がスマホを見ているのではうまくいきません。孤独感を持たせてしまうと、子どもはがんばれないのです。
友だちとの時間を大切にする
また、友だちの存在は励みになりますので、友だちと交流する時間を減らしたり、誘いを断ったりする必要はありません。
ただし、SNSなどでダラダラと繋がって時間を無駄にするのは良くありませんので、子どもと話し合って家庭でのルールをしっかり決め、友だちにも伝えておくことをおすすめします。
(3) 時間がないからといって、焦ってやみくもにやろうとするのはダメ!
必ず計画を立てる
無計画に机に向かっても、時間が浪費されるだけで効率的ではありません。まずは、自分の現在地(実力)と、目標、そこにたどり着くまでの具体的な勉強方法を明確にして、計画的に取り組むことが重要です。
一人ひとり、重点を置く教科も取り組む問題も違います。受験勉強なら、志望校合格のためにどのくらい得点すべきなのかを知り、自分のできていない部分をまずは克服していかなければいけません。そのためにはどの問題集をどのように取り組むのかを決める必要があります。
1日ごとの計画も大事
また、日々の宿題であれば、時間のかかりそうなものは後回しにし、すぐにできそうなことを終わらせる、考える教科は最初の方に取りかかり、暗記系の教科は寝る前に学習する、など順序を考えて取り組むとスムーズに進みます。
部活動や習い事をやめてしまうのは避けたい
![]()
「部活動をやめて時間が空いたから勉強するぞ」となれば良いのですが、たいていの場合、そううまくはいきません。子どもは部活動や習い事があることで、勉強とのバランスをとり、精神的な安定をはかっているからです。
「がんばって続けている」という自信の源でもあります。これが後に受験を乗り切る大きな力になります。また、部活動のがんばりが内申書に反映されたり、実績の証明書を出してくれる習い事もあったりなど、昨今の多様な入試に有利に働くメリットも多いので、できれば最後まで続けたいものです。
成績が伸びないからといって「次のテストで〇点以上取れないと部活動をやめさせる」など強制するようなことは絶対にしてはいけません。親子関係が悪化する原因になります。
どうしても中断せざるを得ない場合は、しっかり話し合って「回数を減らす」「受験が終わったら再開する」など、子どもが納得する着地点を見つけることがポイントです。
勉強と部活動を両立するための時間を生み出す5つの方法
![]()
朝、出かける直前のバタバタした10分間と、夕食後のダラダラした10分間、同じ10分なのに濃さがまったく違う理由は、時間に対する意識の違い。朝の10分と同じように時間を貴重なものとして考えることができれば、勉強の効率が上がります。ここからは、忙しい毎日でも時間を生み出すコツをご紹介します。
(1) 1週間のスケジュールを作成して、使える時間を見える化する
スケジュールを書いてみると気づくのですが、勉強にあてられそうな時間は意外に多いものです。可視化することで、なんとなく過ごしてしまっている時間を有効活用しようという意識につながります。
親が子どもの行動予定を把握しておけば「いつから勉強に取りかかるの」とイライラせずにすみ、家庭がスムーズにまわります。ぜひ親子で一緒にスケジュール作成をしてみましょう。
たとえば曜日ごとに時間軸にそって、睡眠や学校、習い事など固定の時間と、食事やお風呂など基本的な生活時間を書き入れ、残った時間に勉強と自由時間を割り振ります。キツキツに予定を入れ込むのではなく、1週間のうち半日~1日程度の余白を作っておくことが必要です。
友だちに誘われたり、家族と出かけたり、体調不良になったりすることもありますので、予定が総崩れにならないよう余裕を持った計画を。作成したスケジュールは、うまくいかなくなったその都度、修正をしていきましょう。
(2) やることをすべて書き出して、優先順位をつける
何をやればよいかわかっていれば、無駄なくテンポよく取り組むことができます。合わせて、今やらなくて良いこともピックアップし、長期休みに回すなどすれば日々に余裕が生まれます。
たとえば定期テスト対策で数学の問題演習をする場合、「基本問題を2回通りやる」「基本問題と練習問題だけやって発展問題はとばす」など、目標とするテストの点数や習熟度に応じて「やること」を選び取り、集中的にテスト勉強をすることで効果が上がります。
(3) スキマ時間を見つけて、その時間に何をするか決めておく
細切れの時間だからこそ、かえって効果的に学習できる内容もあります。
ペンやノートを使わず取り組める英単語や漢字、語句の暗記です。習い事の送迎の車の中や通学の電車の中、夕食前後の5分など、日々必ず発生する時間を見逃さず習慣化してしまいましょう。
トイレや洗面所に、暗記するものを貼るのも効果的です。歯磨きしながら、ドライヤーで髪を乾かしながら…。毎日必ずすることとセットにすれば、良い意味での「ながら勉強」が可能です。細かな時間を活用する工夫をして、勉強習慣を整えましょう。
また、勉強は「ちょうどの時間」から始める必要はありません。8時から始めよう、ではなく、今すぐ始めれば良いのです。日々のその3分の積み重ねが3年後に大きな差を生みます。そして、そろそろ切り上げようかな、からのあと1問。無理は禁物ですが、その1問のがんばりは基礎を盤石にし、精神力を高めることにもつながります。
(4) 学校の授業は毎回「必ず理解する!」気迫で臨む
最も効率の良い勉強方法は、「授業内で完結する」こと。家に帰って「理解する」ところから勉強を始めるのではなく、「復習する」ところから始められるよう、わからないことはその日のうちに学校の先生に質問して解決することが大切です。
授業内容を理解するためには、ノートをキレイに取ることよりも、先生の言っていることをまずはよく聞くことです。
その上で、繰り返して説明がなされたところ、テストに出そうだとピンときたところ、覚えておくように言われたところを書き留めておけば、テスト前に復習しやすい役立つノートになります。また、授業が始まる前の2~3分で教科書にさっと目を通しておくと、より理解が深まりますのでぜひ習慣にしてほしいと思います。
(5) 好きな教科を作って、勉強のモチベーションを持続させる
よりどころとなる教科があれば、子どもも親も気持ちが安定しやすく焦らなくてすみます。得意な教科ではなくても、ほかよりは勉強しやすい教科、好きな先生の指導教科などでも構いません。「英語が好きなんだね」「数学いつも集中して勉強してるよね」と、親も子どもの「好き」という気持ちを高める声かけをしましょう。
必ずしも「好き=得点」ではありませんので「英語好きだから次のテストもいい点取れそうだね」という励ましはNGです。うまくいかなかったとき、親の期待にこたえられなかったことでかえって自信をなくしてしまう可能性があります。
好きで自信のある教科が1つでもできれば、ほかの教科もがんばれるものです。相乗効果で勉強のスピードもアップしますので、勉強時間を圧縮することにもつながります。