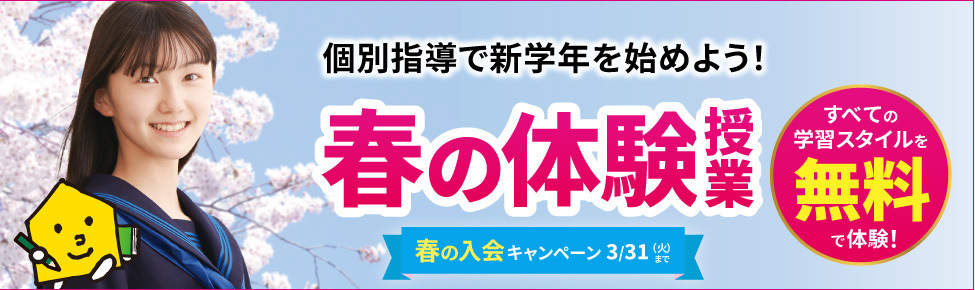総合型選抜の概要
総合型選抜は、大学が求める学生像に合った受験生を選抜する入試方式です。まずは、その特徴や選考方法、他の入試との違いを見ていきましょう。
総合型選抜とは
総合型選抜は、「大学が求めている学生を選抜する」という入試方式です。従来のAO入試から名称と内容が変更され、2021年度の入試からスタートしています。AO入試(アドミッション・オフィス入試)は、志望理由や適性、人柄を重視した入試方式で、学力評価は必須ではありませんでした。しかし、総合型選抜では志望理由や適性に加え、学力評価も必須となり、より多面的な評価が重視されるようになりました。
総合型選抜の選考方法
総合型選抜では、大学が示すアドミッションポリシー(「こんな学生に入学してほしい」という受験生への期待像)に合う学生を選ぶことを重視します。学力だけでなく、学ぶ意欲や入学後の目標、適性なども総合的に評価されるのが特徴です。
選考方法は多岐にわたり、学科試験に加えて、調査書やエントリーシート(志望理由や自己PR、高校時代の活動実績などをまとめる書類)、面接、小論文、プレゼンテーションなどを組み合わせ、受験生の個性や能力を多面的に見ていきます。こうした多様な書類や試験を通じて、大学は自校の方針に合った人物かどうかをより具体的に判断していきます。
※これらの組み合わせはあくまで代表的な例であり、同じ大学、学部でも学科や入試方式、年度によって選考方法が異なる場合があります。必ず最新の募集要項をご確認ください。
国公立大学と私立大学の総合型選抜の違い
総合型選抜には、国公立大学と私立大学で大きな違いがあります。
・国公立大学の場合
総合型選抜における共通テストの扱いには、
- ①共通テストを課す大学
- ②必須ではないが共通テストの成績を利用する大学
- ③共通テストを課さない大学
の3つのパターンがあります。
多くの国公立大学は①の「受験を必須とする」ケースにあたり、そのため総合型選抜であっても一定の学力が求められる点が特徴です。一方で、評価の対象は調査書や志望理由書、面接、小論文など多岐にわたり、学力とあわせて多面的に受験生を見ていきます。
・私立大学の場合
一方、私立大学では、共通テストを課さない大学も多く見られます。その分、人物評価や個別の取り組みが重視される傾向があります。高校時代に取り組んだ課外活動やボランティア、部活動の実績、コンテスト出場歴などが評価対象となり、自己推薦書や志望理由書、面接での自己アピールが合否を左右する大きな要素となります。近年では、プレゼンテーションや活動記録の提出を求める大学も増えています。
総合型選抜以外の選考方法との違い
その他の選考方法には、学校推薦型選抜と一般選抜があります。
・総合型選抜と学校推薦型選抜との違い
学校推薦型選抜は、大きく分けて「公募制」と「指定校制」の2つのタイプがあります。公募制は誰でも応募できる形式で、指定校制は大学が指定した高校からのみ応募できる形式です。学校推薦型選抜は、出身高校の校長の推薦が必要で、出願には出願条件が設定されている場合があり、誰もが出願できるわけではありません。
学校推薦型選抜は高校時代の成績が重視されるのに対し、総合型選抜では学力に偏らず多面的に評価する点が異なります。
・総合型選抜と一般選抜との違い
一般選抜とは、従来の一般入試のことです。、一般選抜は、学力検査の得点によって合否が決まることが多いのに対し、総合型選抜は大学によって選抜方法がさまざまである点が異なります。総合型選抜では小論文や面接に加えて学力検査が課されるなど、多様な選考方法が採用されています。
また、選考時期も異なります。一般選抜の選考は1~3月に実施されているのに対し、総合型選抜は一般選抜より早く9~11月に実施されることが多いです。
※このスケジュールはあくまで代表的な例であり、大学によって3月まで複数回実施している場合もあります。必ず最新の募集要項をご確認ください。
総合型選抜は大学によって選考方法が異なるため、希望する大学の入試要件を早めに把握し、戦略的に対策を行うことが重要です。
総合型選抜のメリット・デメリット
総合型選抜には、他の入試方式にはないメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、総合型選抜のメリットとデメリットを詳しく解説していきます。
総合型選抜のメリット
・学力テストだけで合否の判定を行わない
総合型選抜の大きな特徴は、学力テストの点数だけでなく、志望大学で学びたい意欲や学ぶ資質を備えていることを証明する活動記録が合否の判断材料となることです。例えば、課外でのボランティア活動、生徒会役員や文化祭・体育祭の実行委員を務めた経験なども評価の対象となります。これにより、学力だけでは難しい大学にも合格できるチャンスが生まれます。
・高校からの推薦がなくても受験できる
学校推薦型選抜とは異なり、総合型選抜では高校からの推薦がなくても受験することができます。これは、自分の意志で大学を選び、挑戦できるという点で大きなメリットです。
・一般選抜に比べて合格が早く決まる
総合型選抜は一般選抜よりも早い時期に実施されるため、合格が決まるのも早くなります。これにより、早期に進路が決定し、残りの高校生活を有意義に過ごすことができます。
・一般選抜との併願ができる
多くの大学で、総合型選抜と一般選抜の併願が認められています。これにより、複数の入試方式にチャレンジでき、合格の可能性を広げることができます。
総合型選抜のデメリット
・他の大学と併願できないことが多い
総合型選抜の募集要項に「専願」を条件としている大学が多いため、同時に複数校を受験できないことがあります。専願とは、その大学に合格した場合は必ず入学することを約束する制度です。たとえ併願可能だったとしても、本当に行きたいと思える大学だけを受験することがおすすめです。これは「複数の大学を受験する=入学意思が低い」とみなされることを避けるためです。
・入学後に授業についていけないことがある
大学によっては、一般選抜で入学した学生のほうが基礎学力が高い場合があります。特に国公立や理系学部では、高校で学んだ内容を前提に授業が進むため、学習にブランクがあると授業についていくことが難しくなります。合格後も継続して学習を続けることが大切です。
・一般選抜に比べて合否の基準が曖昧である
総合型選抜では、人間性や活動の実績を評価するため、一般選抜のような明確な点数基準がない場合があります。これは、受験生にとっては合格の見通しが立てにくいというデメリットになります。ただし、この曖昧さは多様な能力を評価するために必要な側面でもあります。
総合型選抜において必要な準備
総合型選抜を成功させるためには、早めの準備と計画的な取り組みが不可欠です。ここでは、総合型選抜に向けた具体的な準備内容とそのスケジュールについて解説します。
提出書類の準備
総合型選抜の準備は、学年に関係なく、早めに取り組むほど余裕を持って進められます。特に「志望理由書」や「事前課題」といった提出書類の作成には、評価の対象となる活動実績を積んだり課題テーマに関する専門知識を身につけたりする必要があります。
そのため、高校2年生の春~夏頃には実績となる活動に取り組んで、その年の秋頃に提出書類の素案を作り始めると、その後の準備がスムーズになります。高校3年生の春に内容をまとめ、添削を重ねながら、夏までに完成させるのが理想的です。
早めに取り組むことで、評定平均を上げたり、必要な資格や活動条件を満たしたりする時間的な余裕も生まれます。評定平均とは、高校での各教科の成績を5段階で評価し、その平均値を算出したもので、多くの大学の出願時に考慮されます。こうした点からも、早期からの準備はとても重要です。
オープンキャンパスへの参加
オープンキャンパスの参加が出願条件となる大学もあるため、志望大学の募集要項は事前に確認しておきましょう。また、大学の雰囲気や授業内容、施設などを実際に体験することで、自分に合った大学を見つけやすくなります。高1・高2のうちから積極的に参加することをおすすめします。
志望校のアドミッションポリシーの確認
アドミッションポリシーは、総合型選抜において重要な評価基準となります。求める学生像は、大学や学部、学科によって異なるため、志望大学のホームページや総合型選抜の募集要項などで必ず確認しましょう。
特に以下の点は要チェックです:
- - 大学・学部が求める人物像
- - 評価対象となる能力・経験
- - 入学後の学びや将来像とのつながり
これらを理解することで、自己PRや志望理由書の作成に活かすことができ、より効果的な準備が可能になります。
総合型選抜に向いている人の特徴
総合型選抜は、特定の能力や。活動実績を持つ受験生に有利な入試方式です。ここでは、総合型選抜に向いている人の特徴を紹介していきます。
将来の夢や目標が明確な人
総合型選抜では、自分の将来の夢や目標が大学のアドミッションポリシーとマッチしていることが重要です。明確な目標を持ち、その実現のために志望大学で学びたいという強い意志がある人に向いています。面接や志望理由書で、自分の将来ビジョンと大学の教育方針との関連性を具体的に説明できることが求められます。
部活動や研究などで成果を出している人
総合型選抜では、受験生の特技や能力を高く評価します。例えば、部活動で全国大会に出場した経験や、科学研究で優秀な成績を収めたなど、特定の分野で際立った実績がある人に向いています。これらの経験は、継続力や協調性、探究心の高さなどを示す良い指標となります。
準備をしっかりと行える人
総合型選抜は提出物が多く、面接や小論文などさまざまな対策を行う必要があります。計画的に準備を進め、自己分析や志望理由の整理、面接練習などに時間をかけられる人に適しています。早めに準備を始め、じっくりと自分の強みを磨く姿勢が求められます。
総合型選抜は、これらの特徴を持つ受験生にとって、自分の能力や個性を最大限にアピールできるチャンスとなります。しかし、これらの特徴に当てはまらなくても、自分の強みを見つけ、それを活かす方法を考えることで、総合型選抜での成功につながる可能性があります。
総合型選抜での成功への鍵と個別指導の重要性
総合型選抜は、従来の学力試験中心の入試とは異なり、受験生の多様な能力や経験を評価する入試方式です。成功の鍵は、早期からの計画的な準備と、自分の強みを最大限に活かすことにあります。志望大学のアドミッションポリシーをよく理解し、自分の経験や能力がどのようにそれに合致するかを明確に示すことが重要です。
大学や学部ごとに出願条件や評価方法は異なるため、求められる準備内容も受験生によって大きく変わります。そのため一人ひとりの志望大学や自分の強みに合わせた対策が必要です。
個別指導Axisでは、志望大学のアドミッションポリシーに基づいて合格までの計画を立て、志望理由書や活動報告書の作成を段階的にサポートします。また、本番で自信を持って臨めるように、小論文の添削や面接練習も繰り返し行います。さらに、必要な教科の学力アップや評定対策も同時に行えるため、総合的な受験準備が可能です。あなたの夢の実現に向けて、一緒に取り組んでいきましょう。
\ アクシスは、全国500校超 /
お近くの校舎へお気軽にお越しください。
この記事を見た人へのオススメ記事
-
高校入学前にやっておくことは?「高1の壁」に潰されない、正しい高校1年生・1学期までの過ごし方
-
大学受験勉強は何から始める?新高3(現高2)必見の勉強の始め方を解説
-
個別指導Axisの校責任者の役割とは?
-
高校生の冬休みの過ごし方!高1、高2も今すぐ本気になるべき理由
-
志望大学・学部の選び方、決め方
-
【高3必見】大学受験で秋から逆転合格を目指す勉強法!夏にサボった人の挽回のポイント
-
志望理由書の書き方
-
【高校生】夏休みの過ごし方!大学受験のために高1、高2がやるべきこと
-
大学受験の志望校の決め方。考え方や時期、注意点などを解説!
-
塾の選び方のポイントを解説。失敗しないために事前にやっておくべきこととは?
-
【春休みの勉強法】周りと差がつく、やるべきこと3選。春期講習の必要性についても解説!
-
大学受験の勉強はいつから始めるべき?理想的な時期と学年別の進め方
-
個別指導塾の料金は?料金の内訳と塾の選び方、確認すべきこと
-
オンライン学習ってどうなの?メリットや通塾との違いを解説!
-
共通テスト 国語、変更点と対策法
-
小論文とは?構成や書き方のポイント、上達への対策【例文付き】
-
大学推薦入試(学校推薦型選抜/総合型選抜)とは?複雑になった仕組みと種類・特徴を解説!
-
「情報Ⅰ」の対策方法を解説!各大学の大学入学共通テスト、新教科の利用状況と対策のポイント
-
アクシスに入塾した決め手とは? 会員生・保護者さまへの入塾アンケート
-
保護者の皆さまからの口コミ・評判お客さまアンケート
-
アクシスってどんな塾?アクシスの教室でインタビュー
-
高校生のリアルな体験談 大学受験おすすめ勉強法
-
難関大挑戦者へのYELL 合格者へのインタビュー&アンケート